

建築業界注目のWLC算定の課題を議論「J-CATシンポジウム」
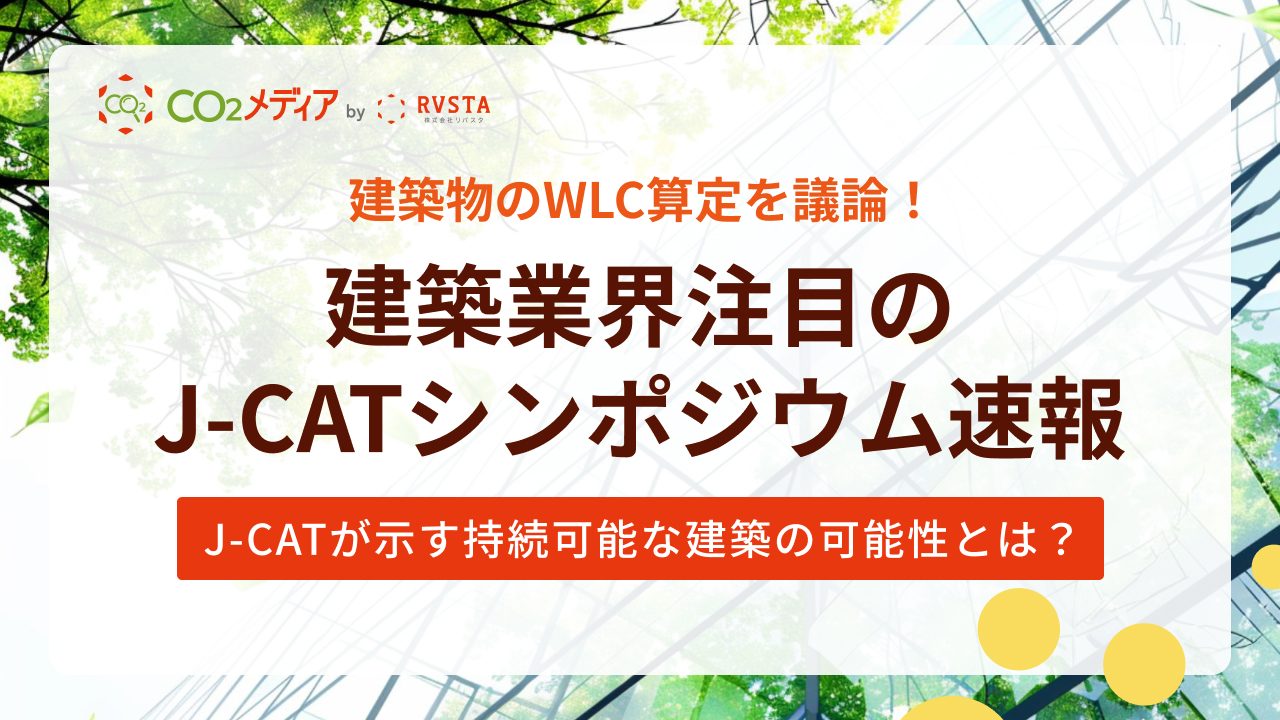
ホールライフカーボン(WLC)算定の課題や動向
住宅・建築 SDGsフォーラム第25回シンポジウム「J-CAT🄬(ジェイキャット)2024.10正式版の全貌~試行版からの改訂内容とゼロカーボンビル評価のこれから~」が2024年11月1日にオンラインで開催されました。一般財団法人住宅・建築 SDGs 推進センター(IBECs)が主催し、一般社団法人日本サステナブル建築協会共催での開催となりました。J-CATの特徴や利用にあたっての注意点、今後のホールライフカーボン(WLC)算定の課題や動向などについて議論され、当日は約1050人がオンラインで参加しJ-CATへの関心の高さを示しました。
算定結果の信頼性を追求
「建築物WLC算定ツール(J-CAT)」は産官学連携による「ゼロカーボンビル推進会議」(委員長:村上周三IBECs顧問)が開発した、原材料の調達から廃棄まで建築物が関係する全段階において排出するCO2量を算定するツールで、2024年5月にβ版を公表。10月に正式版が公開され、11月上旬時点でダウンロード数は300件を超えています。
シンポジウムの冒頭で、村上氏はJ-CAT開発の視点として「緊急性、国際性」「汎用性と使いやすさ」「算定結果の信頼性」の3つを挙げました。このうち「算定結果の信頼性」について村上氏は「これからJ-CATをご利用いただくに当たっては十分勉強して、正しい結果、信頼性のある結果を出していただきたいと思います」と話し、「使いながら改良していく、継続的改良の必要性は関係者の皆さんが了解しておりますので、皆様のご意見をいただきながら、さらにいいものに変えていきたいと思っています」と協力を求めました。
専門家育成の必要性
続いて、10月に公開された正式版について、ゼロカーボンビル推進会議委員長代理でIBECs理事長の伊香賀俊治氏が概要説明を行いました。
伊香賀氏は、ホールライフカーボン評価(WLCA)の実施に向けての背景と国際動向、J-CATの普及・定着のための基盤整備、原単位データ整備のための基盤整備、制度化のための行政基盤の整備支援、将来動向と新たな課題などについて解説しました。
伊香賀氏はJ-CATの普及・定着に向けては、人材育成の重要性に言及。「一般的な建物における部位素材別のGHG排出量の比率に関する基本的な知識、LCAに関連する建築構造設備積算についての総合的知識も必要ですので、そういう意味でしっかり研修を受けていただいて、専門家を育成する必要があると考えております」と話しました。
WLC算定の制度化に言及
ユーザーの立場からもJ-CATに対する要望、期待が述べられました。竹中工務店設計本部専門役の高井啓明氏は、建設会社が抱える課題として、企業全体としてサステナビリティ情報開示を目指して、Scope1、2、3の排出量把握と削減対策を年度単位で集計する一方で、物件ごとに個別にアップフロントカーボン、ホールライフカーボンの算定と削減策の検討を行っていくという二面性があるため、個々の物件の集合体が会社全体のカーボンの算定にはならない状況にあることを指摘しました。
さらにJ-CATに対する要望として、①物件の算定に関わる作業負荷の軽減②算定結果の信頼性、算定者の信頼度、算定費用などの課題に対するルールの整備③当面のジェネリックデータのバリエーションおよびEPDの充実などを挙げました。
高井氏は「アップフロントカーボン、ホールライフカーボン算定の制度化の方向性、スケジュール感を提示していただけるとありがたい。算定結果の申請、開示、今後あり得る規制などについて方向感を示していただけると私たちも大変進めやすくなると思っております」などと今後への期待を述べました。
また、「J-CATとゼロカーボンビル評価、建材・設備EPDのこれから」をテーマとしたパネルディスカッションも行われ、伊香賀氏に加え、内閣官房内閣審議官の今村敬氏、国土交通省住宅局参事官(建築企画担当)の前田亮氏、ゼロカーボンビル推進会議幹事 日建設計エンジニアリング部門ダイレクターの丹羽勝巳氏が参加しました。
今村氏は、ホールライフカーボン算定の制度化について「今後関係省庁の連絡会議を立ち上げて議論したいと思っています。11月に内閣官房に立ち上げて、国土交通省との共同事務局で、関係省庁を集めて議論するということになります。国交省は当然のことながら、経済産業省、環境省、林野庁、金融庁、文部科学省などにも入っていただいて、議論を始めたいと思っております」と述べました。
おわりに
J-CATは、IBECsのホームページから使用登録、ダウンロードが可能です。
詳しくはこちらをご覧ください。
建築物ホールライフカーボン算定ツール(J-CAT®)
https://www.ibecs.or.jp/zero-carbon_building/jcat/index.html
建設業界では、入札段階や工事成績評点で施工時や竣工後の建築物においてCO2排出量の削減が評価され、加点につながる動きが生じています。また、建設会社からCO2排出量を開示し削減方針を示さないと、発注者であるデベロッパーから施工者として選ばれにくくなる状況も起きており、建設会社にとってCO2排出量の管理・削減は喫緊の課題です。
リバスタでは建設業界のCO2対策の支援を行っております。新しいクラウドサービス「TansoMiru」(タンソミル)は、建設業に特化したCO2排出量の算出・現場単位の可視化が可能です。 ぜひこの機会にサービス内容をご確認ください。

この記事の監修

リバスタ編集部
「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、
建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。
「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、
建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。
本ウェブサイトを利用される方は、必ず下記に規定する免責事項をご確認ください。
本サイトご利用の場合には、本免責事項に同意されたものとみなさせていただきます。当社は、当サイトに情報を掲載するにあたり、その内容につき細心の注意を払っておりますが、情報の内容が正確であるかどうか、最新のものであるかどうか、安全なものであるか等について保証をするものではなく、何らの責任を負うものではありません。
また、当サイト並びに当サイトからのリンク等で移動したサイトのご利用により、万一、ご利用者様に何らかの不都合や損害が発生したとしても、当社は何らの責任を負うものではありません。


