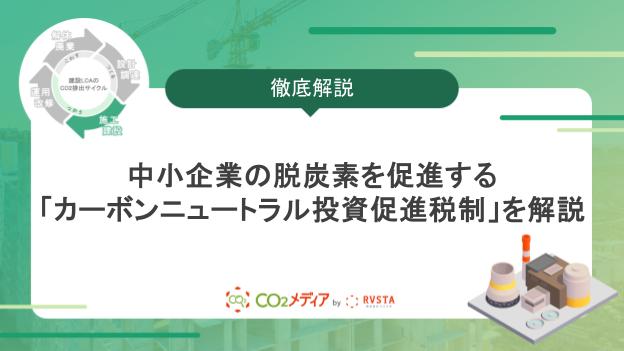
建設業界では、中小企業に対して脱炭素への取り組みへの協力要請が増加している現状があります。一方で、要請に応じて取り組みを推進したけど設備が対応していないことや、取り組みへのコストがかかることを課題として挙げる中小企業も少なくありません。この取り組みを始めやすくする税制として、「カーボンニュートラル投資促進税制」が挙げられます。
本記事では、中小企業の脱炭素を促進するカーボンニュートラル投資促進税制を解説しています。カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の具体的な内容や算出方法、リニューアルされたポイントなども解説しているため、設備投資を検討している方は参考にしてみてください。
目次
中小企業の脱炭素社会に向けた取り組みの現状

中小企業は、脱炭素社会に向けてGHG排出量の削減に取り組んでおり、再生可能エネルギーへの切り替えを含む多様な対策が必要です。
中小企業の脱炭素社会に向けた取り組みの現状として、次のポイントを解説します。
- 企業のGHG排出量の捉え方
- 協力要請が増えている
- 取り組みの課題
それぞれの詳細を見ていきましょう。
企業のGHG排出量の捉え方
企業のGHG排出量は、サプライチェーン全体を通じて以下の3つのカテゴリに分類されます。
| 分類 | 内容 |
| Scope1 | 自社が直接排出するGHG |
| Scope2 | 自社が間接排出するGHG |
| Scope3 | 原材料仕入れや販売後に排出されるGHG |
Scope1は、企業が直接排出するGHGを指します。製品製造過程での石油の化学的加工や、石炭を燃焼させて熱エネルギーを得る際に排出されるCO2などが対象です。
Scope2は、他社から供給された電気・熱・蒸気の使用による間接的な排出を指します。典型的な例は、オフィスビルで使用する電力会社からの電気供給です。供給される電気が石炭火力発電など化石燃料由来である場合、排出量がScope2に見込まれます。
Scope3は、原材料の調達から製品の廃棄まで、サプライチェーンの上流・下流全体での排出が対象です。具体的には、上流工程として原材料メーカーから自社施設への輸送、下流工程として販売会社の活動や消費者による製品使用、廃棄時のスクラップ処理などが含まれます。
また、従業員の通勤や出張に伴う排出もScope3の対象です。Scope3は企業活動に関連する最も広範な排出量を捉える指標とされています。
協力要請が増えている
中小企業を取り巻く脱炭素への取り組みは、近年急速に重要性を増しています。特に注目すべきは、取引先からの協力要請が増加している点です。
例えば、脱炭素協力を要請された企業の割合は、2020年の7.7%から2022年には15.4%に倍増しました。この2年間での大幅な増加は、サプライチェーン全体での脱炭素の動きが加速していることを示しています。
変化の背景として、二つの主要な要因があります。1つは取引先企業、特に大企業からの要請増加です。サプライチェーン全体でのCO2削減が求められる中、取引先との協力関係の構築が欠かせません。もう1つは、昨今のエネルギー価格高騰の影響です。
これにより、中小企業でも脱炭素への具体的な取り組みや新たな対策を検討する必要がある企業が増えています。脱炭素に向けた協力要請は、今後もさらに加速していくことが予想されます。
取り組みの課題
中小企業の脱炭素への取り組みが増加する一方で、実施・検討過程でさまざまな課題に直面する企業が増えています。
最も顕著な課題が、対応コストが高い経済的な問題です。省エネ設備や再生可能エネルギーの導入には、多額の初期投資が必要となることが多く、中小企業にとって大きな負担となりかねません。
また、現有設備では対応が難しい技術的な課題も増加傾向です。既存の生産設備やシステムを脱炭素に対応させることが困難なケースが多く見られます。
さらに、Scope3排出量の算定に関する課題も重要です。Scope1やScope2と比べ、Scope3は原材料調達から製品使用、廃棄に至るまで、排出される場面が多様な特徴があります。そのため、正確な排出量の把握と算定が極めて困難です。
中小企業が抱えている取り組みの課題は、脱炭素への取り組みを遅らせる要因です。
カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の概要
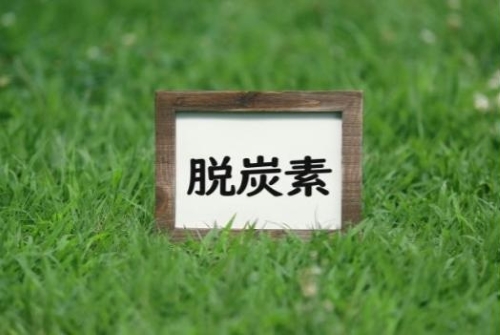
脱炭素社会を実現するため、対応設備の導入が必須です。この目的で、国は中小企業が脱炭素に取り組みやすい環境を整備するための投資促進税制を制定しました。
カーボンニュートラルに向けた投資促進税制に関して、次の内容で解説します。
- カーボンニュートラルに向けた投資促進税制とは
- 税額控除率について
- 取り組み内容のイメージ
- 炭素生産性の向上要件の数値算出方法
- 申請の流れ
それぞれの内容を詳しくみていきましょう。
カーボンニュートラルに向けた投資促進税制とは
脱炭素の実現に向けて、民間企業による脱炭素投資の加速が不可欠です。そのため、産業競争力強化法に基づく投資促進税制が設けられました。
この税制は、企業が生産工程などで脱炭素と付加価値の向上を両立する設備を導入する際、最大14%の税額控除や50%の特別償却を受けられるように設計されています。企業の積極的な設備投資を促進し、環境負荷の低減と経済成長の両立を目指しています。
特別償却制度では、設備取得年度で通常の減価償却に加えて50%の追加償却が認められます。一方、税額控除制度では、設備取得年度の法人税額から、取得価額の最大10%相当額を直接控除可能です。
適用期限は、2026年3月31日までにエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画の認定を受けた企業が対象で、認定日から3年間です。税制措置により、企業の脱炭素投資を促進し、2050年の脱炭素社会の実現を後押しすることが期待されています。
税額控除率について
カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の税額控除率は次に示す内容の通りです。企業区分、および認定された計画全体の炭素生産性の向上率によって税額控除率が異なります。
| 企業区分 | 炭素生産性の向上率 | 税制措置 |
| 中小企業者等 | 17% | 税額控除14% 又は 特別償却50% |
| 10% | 税額控除10% 又は 特別償却50% | |
| 中小企業者等以外の事業者 | 20% | 税額控除10% 又は 特別償却50% |
| 15% | 税額控除5% 又は 特別償却50% |
企業区分の中小企業者に該当する要件は、租税特別措置法第42条の12の7第6項第1号に規定されており、法人の場合、資本金の額または出資金の額が1億円以下であることが主な要件です。
また、資本または出資を有しない法人は、常時使用する従業員の数が1,000人以下であることが要件とされています。個人事業主の場合は、常時使用する従業員の数が1,000人以下であれば中小事業者として認定されます。
参照:エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画(カーボンニュートラルに向けた投資促進税制)の申請方法・審査のポイント|経済産業省
取り組み内容のイメージ
カーボンニュートラルに向けた投資促進税制では、炭素生産性の向上を重視した計画策定が求められます。企業は設備投資による効果を含めて、3年以内に炭素生産性を15%以上、または、中小企業者等は10%以上を向上させる計画を作成し、認定を受けなければなりません。
まず基準年度の炭素生産性を算出し、そこから3年間にわたってさまざまな施策を実施しながら、毎年の炭素生産性を測定します。目標年度で15%以上の向上が達成できれば、税制優遇の対象です。
取り組みの具体例としては次の内容が挙げられます。
| 年度 | 取り組み内容例 |
| 1年目 | 古くなったファンを交換 |
| 2年目 | 主用機械装置を燃費の良い最新設備に交換 |
| 3年目 | 太陽光発電設備の導入 |
また、計画に記載された個別の設備も、設備の導入前後で事業所の炭素生産性を1%以上向上した場合には、税制措置の適用を受けられます。ただし、LEDなどの照明設備やエアコンディショナーなど一般的に広く流通している設備は、税制措置の対象外です。
炭素生産性の向上要件の数値算出方法
炭素生産性は次の方法で算出できます。
| 炭素生産性 = 付加価値額 / エネルギー起源二酸化炭素排出量
※付加価値額 = 営業利益 + 人件費 + 減価償却費 |
算出された炭素生産性を比較する式は次の通りです。
| ((目標年度の炭素生産性 – 基準年度の炭素生産性)/ 基準年度の炭素生産性) × 100 |
炭素生産性の向上要件の数値算出では、まず目標年度と基準年度を適切に設定する必要があります。目標年度は計画開始から3年以内の年度に設定し、基準年度は原則として計画開始の直前の事業年度です。
また、電気事業者等の電気メニューの切り替えによる温室効果ガスの削減は、エネルギー起源二酸化炭素排出量の算定に含められません。その上、目標年度の炭素生産性を算出する際には、基準年度の算出に使用した排出係数を用いる必要があります。
さらに、国内認証排出削減量および海外認証排出削減量は、計算に加えられません。
算出する場合の単位は次の内容に沿って設定する必要があります。
| 目標年度 | 基準年度 | 適用できるケース |
| 事業所 | 事業所 | ・適応計画全体の炭素生産性を算定する場合
・設備の導入による効果を算定する場合 |
| 事業者全体 | 事業者全体 | ・適応計画全体の炭素生産性を算定する場合 |
| 事業所 | 事業者全体 | ・適応計画全体の炭素生産性を算定する場合
・設備の導入による効果を算定する場合 ・新設の事業所など、基準年度の炭素生産性の数値が存在しない場合 |
ただし、事業所を単位として算定できるのは、年間のエネルギー使用量が3,000kl以上の事業所である場合、または申請者が中小企業者等である場合に限ります。
申請の流れ
申請は以下の流れで行います。
- 事前相談
- 計画の申請
- 計画の認定
- 税制対象投資の実施
- 税務報告
- 実施状況報告書提出
申請は、事前相談から始まります。計画の認定を予定している時点から約2カ月前に、事業を所管している省庁への事前相談を行わなければなりません。事前相談は、スムーズな申請手続きを確保し、必要な修正や調整を事前に行うための重要なステップです。
申請手続きは、効率化と簡素化を図るために、原則としてWeb申請のみで行われます。Web申請により、申請者の手続き負担を軽減するとともに、処理の迅速化も実現しています。
リニューアルされたポイント

2023年度の改正で、カーボンニュートラルに向けた投資促進税制は次の内容でリニューアルされています。
- 控除率の引き上げ
- 適用期間の長期化
以下にそれぞれの内容を詳しく解説します。
控除率の引き上げ
カーボンニュートラルに向けた投資促進税制のリニューアルでは、控除率が引き上げられました。2023年まで、税制措置は炭素生産性の向上率のみに基づいていましたが、新制度では企業の種類による新たな区分が導入されました。
具体的には、中小企業者と中小企業者以外の事業者に区分され、それぞれに異なる税制措置が適用されることになりました。見直しの背景には、サプライチェーン全体での脱炭素の加速が求められる社会的要請があります。
特に、中小企業がこれまで直面してきた設備投資等のコスト面での課題に対応するため、中小企業向けの控除率を手厚くする改正が行われました。中小企業は従来よりも有利な条件で税制優遇を受けられるため、脱炭素への取り組みを促進しやすい環境が整備されています。
このリニューアルは、企業規模に応じた経済的負担を考慮し、より細かく支援を分けたものです。
適用期間の長期化
カーボンニュートラルに向けた投資促進税制のリニューアルとして適用期間の長期化が実施されました。従来は設備投資の検討から導入までを3年以内で完了することが求められていましたが、3年以内の期間設定では企業の実態に即していない課題がありました。
特に大規模な設備投資では、検討から判断、さらに実行から稼働開始までに相当な時間がかかることが一般的です。これにより、企業は余裕を持って投資判断を行い、確実な設備導入が可能になります。
検討から認定までの期間を2年以内とし、その後の認定から導入・稼働までの期間を認定日から3年以内と設定されました。企業は余裕を持って投資判断を行い、確実な設備導入の実施が可能です。リニューアルは、より現実的な事業計画の立案と実行を支援する制度設計です。
まとめ

本記事では、建設業界の方向けに、中小企業の脱炭素を促進する、カーボンニュートラルに向けた投資促進税制を解説しました。中小企業では、脱炭素社会に向けてGHG排出量の削減が求められています。再生可能エネルギーへの切り替えなども含めて、さまざまな対策が必要です。
中小企業の脱炭素への取り組みが増加する一方で、実施・検討過程でさまざまな課題に直面しています。その中で最も顕著な課題が、対応コストが高い経済的な問題です。この対策として、中小企業が脱炭素に取り組みやすい環境を整えられるように投資促進税制が国により制定されました。
カーボンニュートラルに向けた投資促進税制は、企業が生産工程等の脱炭素と付加価値向上を両立する設備を導入する際に、最大14%の税額控除または50%の特別償却が適用されます。
本記事ではカーボンニュートラルに向けた投資促進税制の具体的な内容や算出方法、リニューアルされたポイントなども解説しているため、設備投資を検討している方は参考にしてみてください。

この記事の監修
リバスタ編集部
「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。











