

オンサイトPPAとは|オフサイトPPAとの違いやメリット・デメリット、建設業との関連について
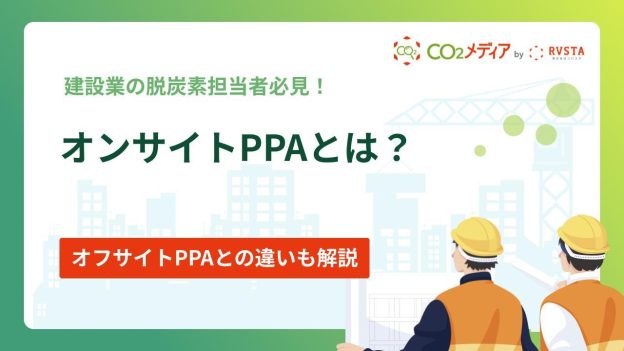
昨今、太陽光発電設備のコストを抑えて導入できる「オンサイトPPA」が注目されています。オンサイトPPAは初期費用だけではなく、メンテナンスなどのランニングコストもかからないのが特徴です。
本記事では、建設業界の方向けにオンサイトPPAのメリット・デメリットを解説します。また、オフサイトPPAとの違いや実際に導入した例も紹介しているので、今後導入を検討している建設業者の方はぜひ参考にしてください。
オンサイトPPAとは?

そもそもオンサイトPPAとはどのようなものなのか、オンサイトPPAの概要やオフサイトPPAとの違いについて解説します。
オンサイトPPAの概要
オンサイトPPAは、企業が保有する敷地内に太陽光発電設備を導入する際の新たな選択肢として注目されており、太陽光発電設備の初期費用を抑えて導入できるのが特徴です。
オンサイトPPAの基本的な流れは、再エネ由来の電力を必要とする企業がエネルギーサービス事業者と契約を結び、エネルギーサービス事業者が企業の敷地内に太陽光発電設備を設置します。発電した電力は割安な電気料金で調達できるため、企業のエネルギーコスト削減にもつなげられることがメリットです。
太陽光発電設備の所有権はエネルギーサービス事業者が有しているため、企業側にとっては太陽光発電設備の導入費用がかからないメリットもあります。また、原則として維持管理やメンテナンスの手間も発生しないため、企業は本業に集中しながらも再生可能エネルギーの活用を進められます。
オフサイトPPAとの違い
オンサイトPPAとオフサイトPPAの違いは、太陽光発電設備の設置場所です。オフサイトPPAは企業の敷地外に発電設備を設置し、送電線を通して電気を供給します。一方、オンサイトPPAは企業の敷地内に設備を設置するのが特徴です。
オンサイトPPAではPPA事業者から企業へ直接電気が供給されますが、オフサイトPPAは小売電気事業者を仲介しなければなりません。そのため、オフサイトPPAは送電にかかるコストを小売事業者に支払わなければならず、オンサイトPPAと比較して電気料金が高価になる傾向にあります。
ただし、太陽光発電設備を導入する際の初期費用やメンテナンス費用がかからない点は、オンサイトPPAとオフサイトPPAに共通するメリットです。どちらの方式でも、企業は再生可能エネルギーの費用負担を抑えながら活用できます。
関連記事:バーチャルPPAとはなにかわかりやすく解説|仕組みとメリットについて
オンサイトPPAのメリット

オンサイトPPAの主なメリットは、以下の4点です。
- 太陽光発電の導入費用を軽減できる
- CO2排出量を削減できる
- 電気料金の節約につながる
- 補助金制度の対象になる
ここでは、オンサイトPPAのメリットについてそれぞれ詳しく解説します。
太陽光発電の導入費用を軽減できる
オンサイトPPAのメリットのひとつは、太陽光発電の導入費用を大幅に軽減できる点です。企業が太陽光発電を導入する場合、発電設備の費用として数百万円から数千万円、場合によっては数億円の初期投資が必要です。
一方でオンサイトPPAは、発電設備費を発電事業者が負担するため、初期費用がゼロになります。
さらに、太陽光発電設備のメンテナンスや管理費用も発電事業者が負担するため、継続的なコスト削減が可能です。また、台風や地震などの自然災害による設備の破損など想定外のコストも企業側が負担する必要がなく、リスクを抑えながら再生可能エネルギーを活用できます。
経済的負担の軽減により、企業は本業への投資を優先しながらも、持続可能なエネルギー利用へと移行が可能です。
CO2排出量を削減できる
オンサイトPPAのもうひとつのメリットは、CO2排出量を削減できる点です。太陽光発電は発電過程でCO2を発生させない再生可能エネルギー源であるため、オンサイトPPAモデルを活用することで環境保護につながります。
つまり、企業が事業活動で使用する電力を、化石燃料由来の電力から太陽光発電による電力に切り替えることで温室効果ガスの排出量を大幅に削減します。その結果、企業のカーボンフットプリントを低減し、環境負荷の少ない事業運営が可能です。
また、オンサイトPPAの太陽光発電を導入することで、環境問題に積極的に取り組む企業としての社会的評価やイメージ向上も期待できます。SDGsやESGへの取り組みが重視される現代で、再生可能エネルギーの導入は企業価値を高めて、取引先や消費者からの信頼獲得にもつながる要素です。
電気料金の節約につながる
オンサイトPPAのメリットとして、再エネ賦課金がかからないことによる電気料金の節約も挙げられます。
通常の電力購入では、再生可能エネルギーの普及促進のための賦課金が電気料金に上乗せされます。しかし、オンサイトPPAで発電された電気は、企業の敷地内で自家消費されるため、再エネ賦課金が免除されます。
さらに、通常の電力購入時にかかる燃料調達費や仲介料などの各種コストも一切不要です。企業は長期的かつ安定的な電気料金の削減を実現でき、電力コストを削減した効率の良い事業運営が可能です。
補助金制度の対象になる
オンサイトPPAのメリットとして、補助金制度の対象になることも挙げられます。オンサイトPPAモデルでは、国や自治体が提供する再生可能エネルギー導入に関する各種補助金制度を活用できます。
また、補助金を活用することで、PPA事業者側の太陽光発電所の導入費用を大幅に削減可能です。発電設備の初期投資が抑えられることにより、PPA事業者は事業の採算性を向上させられます。
結果としてPPAの導入コストの削減により、最終的に企業に提供される電気料金も安くなります。つまり、補助金の恩恵は電気を使用する企業側にも還元され、より安価な再生可能エネルギーを調達できるのがメリットです。
オンサイトPPAのデメリット

オンサイトPPAのデメリットとして、以下3つが挙げられます。
- 審査を受けなければならない
- 契約期間の縛りがある
- 契約終了後のランニングコストがかかる
オンサイトPPA導入を検討している方は、メリットだけでなくここで紹介するデメリットも把握しておかなければなりません。
審査を受けなければならない
オンサイトPPAを導入する際のデメリットとして、事前審査の必要性が挙げられます。企業がオンサイトPPAを検討する場合、PPA事業者による厳格な審査を受けなければなりません。
審査では太陽光発電設備を設置する場所の条件や、企業の経営状況などが詳細に評価されます。審査基準を満たさない場合は、オンサイトPPAの導入が認められないため注意が必要です。また、企業の財務状況に不安がある場合、長期契約の相手として適切でないと判断される可能性があります。
なお、物理的な条件も重要な審査対象です。
- 企業の敷地が狭い
- 塩害地域にある
- 屋根の形状や強度が太陽光パネルの設置に適さない
上記のように、技術的に発電所の設置が困難と判断される状況では、PPA事業者から契約を断られる可能性もあります。
契約期間の縛りがある
オンサイトPPAのデメリットは、長期間にわたる契約の縛りがあることです。PPAサービスを提供している事業者によって多少の違いはあるものの、一般的なPPA契約の期間は20年程度と非常に長期間に設定されています。
長期契約には拘束力があり、企業側の事情が変化しても契約内容を容易に変更できません。例えば、事業規模の縮小や業態変更によって電力使用量が大幅に減少したとしても、原則として契約を変更できないケースがほとんどです。
長期にわたる固定的な契約は、企業の事業戦略や経営計画に大きな影響を与える可能性があります。企業がオンサイトPPAで太陽光発電を導入する前には、長期的な事業計画を慎重に立てておくことが重要です。
契約終了後のランニングコストがかかる
オンサイトPPAのデメリットとして見落とされがちなのが、契約終了後のランニングコストです。オンサイトPPAは、契約期間中は敷地内に設置された再生可能エネルギー電源のメンテナンス費用を発電事業者側が負担するメリットがあります。
一方で、長期間の電力購入契約が終了した後、太陽光発電設備は需要家である企業に譲渡されるのが一般的です。譲渡された時点から、設備のメンテナンスや修理にかかる費用はすべて需要家側の自己負担になります。老朽化した設備の管理費用は年々増加する傾向にあり、予想以上の経済的負担となる可能性があります。
さらに、将来的に発電設備が使用不能になった場合や、経営戦略の変更などにより撤去が必要になった場合、需要家は発電設備の廃棄に関する責任と費用を負わなければなりません。
オンサイトPPAと建設業の関連性

ここでは、オンサイトPPAと建設業の関連性を以下3つの観点で解説します。
- 工場や施設の電力コスト削減
- 環境負荷の低減と企業イメージの向上
- エネルギー価格変動リスクの低減
それぞれのポイントを詳しく解説します。
工場や施設の電力コスト削減
工場や施設の電力コスト削減で、オンサイトPPAと建設業の関連性が重要な役割を果たします。建設業の知見を活かすことで、より効率的かつ安全なオンサイトPPAの導入が可能です。
工場の屋根上に太陽光発電設備を設置・運営し、同じ工場に「生グリーン電力」を供給するモデルがあります。
「生グリーン電力」とは、発電所から需要家へ直接送電されるグリーン電力のことです。中間業者を介さないため、効率的かつコスト効果の高い電力供給が実現できます。
発電設備の設置では、建設事業者としての専門知識が大きな強みです。既存の屋根の構造や強度を詳細に把握し、考慮した発電設備の最適配置を設計できます。建物の特性を理解した上で適切な太陽光パネルの選定や配置、耐荷重計算などを行うことで、安全性と発電効率を両立した設備の導入が可能です。
環境負荷の低減と企業イメージの向上
近年、SDGsやESG投資の広がりとともに、持続可能な社会への取り組みに対する関心が高まっています。建設業界でも、環境配慮型の事業展開が求められる中、オンサイトPPAの導入は具体的な環境貢献策のひとつです。
また、建設会社が自社の工場や事務所にオンサイトPPAを導入することで、CO2排出量を削減し、環境負荷を低減できます。さらに、取り組みを取引先や顧客に積極的にアピールできれば、環境意識の高い企業としてのイメージ向上にもつながります。
他にも、具体的な再生可能エネルギーの発電量や削減したCO2排出量などを数値で示すことで、環境への貢献を可視化し、企業の社会的責任を果たしていることの証明としても利用可能です。
エネルギー価格変動リスクの低減
建設業界は多くの電力を消費するため、エネルギー価格の変動が経営に大きな影響を与えることがあります。オンサイトPPAを導入することで、建設会社は自社施設に発電設備を設置し、安定した価格で電力を調達できます。そのため、世界情勢や資源価格の変動に左右されがちな従来の電力調達と比較して、エネルギー価格の変動リスクを大幅に低減可能です。
さらに、エネルギー自給の強化は、供給不安定時のリスクヘッジとしても機能します。工場運営など電力消費量の多い事業を展開している建設企業にとっては、エネルギーコストが経営を左右する重要な要素です。電力消費量の多い建設企業ほど、オンサイトPPAによる価格変動の抑制により、大きな経済的メリットを享受できます。
建設業界におけるオンサイトPPAの導入事例

建設業界におけるオンサイトPPAの導入事例として、次の3つの企業を紹介します。
- 大林組
- 東急建設
- 西松建設
それぞれの事例を参考にしてみてください。
大林組
株式会社大林組(本社:東京都港区、社長:蓮輪賢治)のグループ会社である株式会社大林クリーンエナジー(本社:東京都港区、社長:三浦良介)と、同じくグループ会社で製材・集成材製造を行う株式会社サイプレス・スナダヤ(本社:愛媛県西条市、社長:砂田和之)は、「オンサイトPPA(第三者所有モデル)(※1)」により、再生可能エネルギー電力の供給に関する契約締結について合意し、事業に着手しました。
本事業は、サイプレス・スナダヤが愛媛県西条市に保有する東予インダストリアルパーク工場の屋根上に、大林クリーンエナジーが太陽光発電設備約2MWを設置・運営し、同工場に「生グリーン電力(※2)」を供給する、自家消費型のオンサイトPPAです。
電力供給開始予定は、2024年12月で、年間自家消費量約184万kWhを想定しています。これにより、工場の電力需要の約15%を賄うことが可能で、年間約970tの温室効果ガス排出量削減が見込まれます。また、大林組の建設事業者としての知見を活かし、既設屋根の強度を考慮した発電設備の最適配置を行っています。
引用:大林組、大規模製材工場でオンサイトPPAによる再エネ電力供給事業に着手|2024.01.09|BuildApp News
東急建設
東急建設(東京都渋谷区)はこのほど、太陽光オンサイトPPAサービスの提供を開始し、第一号案件の契約を締結した。
同サービスは、同社が発電事業者として顧客の敷地内に太陽光発電設備を設置・運営し、当該発電設備で発電した電力を顧客に供給するもの。顧客は、使用電力量に応じたサービス料金(固定単価)を支払うことで、初期費用なしで再生可能エネルギーの電力を利用できる。
第一号案件は、東急リネン・サプライ(東京都品川区)へのPPAサービス提供。東急リネン・サプライが保有する佐野工場の屋根上に、東急建設が出力156.4kWの太陽光発電設備を新設する。2024年3月の運転開始を予定しており、初年度の効果として、使用電力量の約28%が再エネ電力に置き換わり、約25%(約63.5t)のCO2排出量削減を見込んでいる。
引用:東急建設、太陽光オンサイトPPAの提供を開始|2023.06.21|新建ハウジングDIGITAL
西松建設
当社は、オンサイトPPAの新たなスキームとなる余剰電力活用型オンサイトPPAの運用を2024年7月に開始し、当社施工の物流施設にて発電される再エネ電力のうち物流施設内で消費しきれない電力(以下、余剰電力)を自社施設に供給することで、太陽光発電設備から供給される再エネ電力を100%有効活用できるようになりました。
当社は、PPAサービス事業者としてオンサイトPPAの運用を開始しておりましたが、物流施設単体では太陽光で発電される電力の50%程度しか活用できていない課題がありました。このため今回、当社が所有・運営する学生寮4施設(日吉国際学生寮、湘南藤沢未来創造塾学生寮(Hヴィレッジ)、高輪国際学生寮、NCRe玉川学園)へこの余剰電力を供給し100%有効活用することで、西松建設全体での再エネ電力使用比率を高めることを可能にしました。
この取り組みにより、学生寮4施設の電力使用量の約20%(約22万kWh/年)が余剰電力で賄われ、約94tのCO2削減に寄与します。削減対象は、当社のスコープ2(需要4施設の共用部)およびスコープ3(需要3施設の専有部※NCRe玉川学園は専有部含まず)となります。
引用:余剰電力活用型オンサイトPPAの運用開始|2024.07.31|西松建設
まとめ

本記事では、建設業界の方向けにオンサイトPPAのメリット・デメリットを解説しました。オンサイトPPAとは、企業が保有する敷地内に太陽光発電設備を導入する際の新たな選択肢として注目されている仕組みです。オンサイトPPAの特徴は、太陽光発電設備の初期費用を抑えて導入できる点にあります。
通常の電力購入では、再生可能エネルギーの普及促進のための賦課金が電気料金に上乗せされますが、オンサイトPPAで発電された電気は企業の敷地内で自家消費されるため、賦課金が免除されることもメリットです。
一方でオンサイトPPAには、審査を受ける必要があることや、長期間の契約期間があることなど、いくつかのデメリットもあるため注意が必要です。
本記事では、オンサイトPPAを導入している企業の事例を3つ紹介しているので、導入を検討している方は参考にしてください。
建設業界では、入札段階や工事成績評点で施工時や竣工後の建築物においてCO2排出量の削減が評価され、加点につながる動きが生じています。また、建設会社からCO2排出量を開示し削減方針を示さないと、発注者であるデベロッパーから施工者として選ばれにくくなる状況も起きており、建設会社にとってCO2排出量の管理・削減は喫緊の課題です。
リバスタでは建設業界のCO2対策の支援を行っております。新しいクラウドサービス「TansoMiru」(タンソミル)は、建設業に特化したCO2排出量の算出・現場単位の可視化が可能です。 ぜひこの機会にサービス内容をご確認ください。

この記事の監修

リバスタ編集部
「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、
建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。
「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、
建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。
本ウェブサイトを利用される方は、必ず下記に規定する免責事項をご確認ください。
本サイトご利用の場合には、本免責事項に同意されたものとみなさせていただきます。当社は、当サイトに情報を掲載するにあたり、その内容につき細心の注意を払っておりますが、情報の内容が正確であるかどうか、最新のものであるかどうか、安全なものであるか等について保証をするものではなく、何らの責任を負うものではありません。
また、当サイト並びに当サイトからのリンク等で移動したサイトのご利用により、万一、ご利用者様に何らかの不都合や損害が発生したとしても、当社は何らの責任を負うものではありません。


