

バーチャルPPAとはなにかわかりやすく解説|仕組みとメリットについて
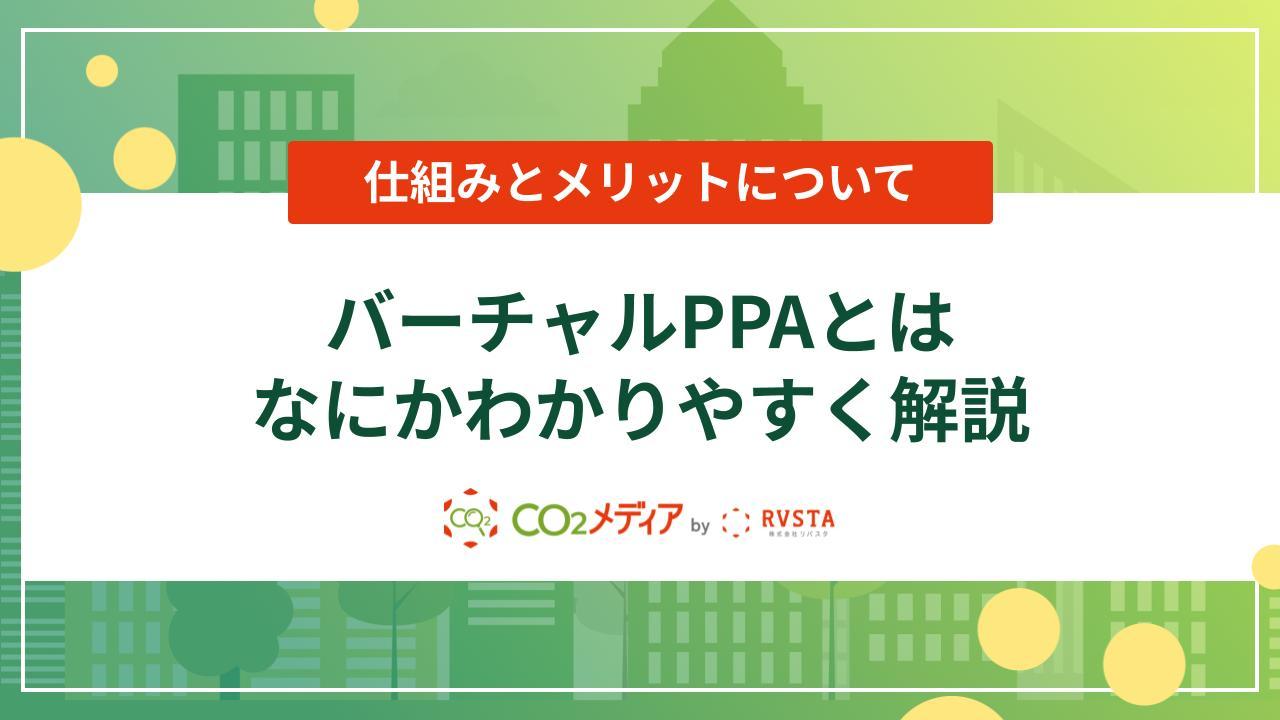
環境汚染・資源枯渇など環境に関する問題は年々深刻化しています。そのようななか、注目を集めているのが再生可能エネルギーであり、関連性が深いのが「バーチャルPPA」です。今回は、バーチャルPPAの概念や仕組み、バーチャルPPAのメリットとデメリット、企業のバーチャルPPAの導入事例などについて、詳しく解説します。
バーチャルPPAの概要

バーチャルPPAのPPAとは、「Power Purchase Agreement」の略称で、日本語訳で「電力購入契約」と訳されます。
PPAにおける電力は、再生可能エネルギーである太陽光・風力などの発電によって発生した再エネ由来の電力を指します。この再エネ由来の電力を売却する発電事業者・購入する購入者との間で行う売買契約がPPAです。この契約を結び料金を支払えば、発電機器を持っていない人でも再生可能エネルギーを利用したことになります。
再エネ由来の電力は電力と共に環境価値を持っています。この環境価値は証書と切り離すことも可能であり、証書として取引されています。このPPAを利用したバーチャルPPAとは、再生エネ発電により生じた再エネ由来の電力自体の取引は行わず、再エネ電力が持つ環境価値だけを証書として取引する手法です。
バーチャルPPA取引によって「温室効果ガス排出などによって生じる地球環境にかかる負担」を回避した証明になり、非FIT非化石証書(再エネ指定)の証書が電力購入者に付与されます。
バーチャルPPAの仕組み
バーチャルPPAは、電力需要側と発電事業者が契約を結び売買を成立させる仕組みで、固定価格・市場価格の差額による差金決済といわれる精算方法で金額を決定します。再生可能エネルギーの発電にかかるコストを主軸に、契約価格(固定価格)を決定し、市場価格を差し引いた価格を需要側が支払う仕組みです。
バーチャルPPAの仕組みをまとめると、以下のような内容になります。
|
バーチャルPPAにおいて差金決済が採用されている理由は、発電事業者の収入安定化、再エネ発電事業の持続可能性の向上です。
日本国内のバーチャルPPAは、基本的に需要家と発電事業者の間に小売電気事業者が間に入ります。それにより差額の精算に関する業務代行、需要家の代行で差額の一部を負担する仕組みです。
ただし、2022年4月1日以降に始動した発電設備は、需要側が発電事業者と直接バーチャルPPAの契約をできるようになり、このケースだと仲介が受けられません。そのため、この場合は通常の購入方法ではなく、需要サイドが自身で市場価格の変動に合わせて、差額を精算する方法になります。
バーチャルPPAとフィジカルPPAとの違い
PPAは、バーチャルPPA以外に「フィジカルPPA」という手法も存在します。この2つの違いは以下のとおりです。
| バーチャルPPA |
|
| フィジカルPPA |
|
バーチャルPPAはフィジカルPPAと異なり、電力の購入・消費がなくても環境価値の獲得ができ、脱炭素・環境保護に一役買ったという証明になるのです。
また、建設業界では、プロジェクト期間が限られているため、長期契約が必要なフィジカルPPAではなく、柔軟に導入できるバーチャルPPAがニーズに合致する可能性が高いといえます。
バーチャルPPAのメリット

バーチャルPPAの契約をすることによって、どのようなメリットが発生するのでしょうか。以下よりバーチャルPPAの代表的なメリットについて説明します。
既存の契約を継続できる
バーチャルPPAは契約しても既存の電力契約には何も影響がなく、既存の電力契約の解約手続きも不要です。
バーチャルPPAで購入するのは再生可能エネルギーとして発電された電力の環境価値のみで、電力を購入するわけではありません。先述したフィジカルPPAのように環境価値に加えて再エネ由来の電力そのものも購入する場合は、電力購入先を変更するため既存の契約を破棄して、新たな契約の手続きをする必要があります。
しかしバーチャルPPAは、実際の電力を購入・消費するわけではないため、電力の供給は既存のままで問題ありません。
複数の事業所を運営している企業で、電気代の節約のため電力契約を一括しているところもあります。そのような企業がフィジカルPPAに移行する場合、また新たな契約をしなくてはならず、電気代の節約ができなくなるでしょう。しかし、バーチャルPPAであれば、既存の契約を継続したまま導入が可能です。
環境への配慮
バーチャルPPAを導入することで、環境へ配慮していることの証明になります。地球温暖化・環境汚染の問題が深刻化する近年、企業も環境に配慮した経営姿勢を見せないと、投資家・消費者からの信頼度が得られない風潮になっています。
バーチャルPPAは、非FIT非化石証書(再エネ指定)という証明書が付与され、再生可能エネルギーの利用を証明することとなるため、投資家へのアピールにもなります。
再エネの自由度が高くなる
再エネ由来の電力を使用する営業所、しない営業所を自由に選べることも、バーチャルPPAのメリットです。バーチャルPPAは、通常の電気契約・フィジカルPPAと異なり、直接的に電力の供給を受けているわけではなく、環境価値のみを購入します。
そのため、企業で複数の営業所を構えている場合、どの営業所を再エネ電力対応にするかなどの選択が可能です。また、購入した環境価値を複数の営業所に分配することも可能なため、どの営業所の環境価値を多めにするかなどの調整もできます。
環境価値を持っていた営業所が閉鎖することになっても、運営を継続する別の営業所に環境価値を移行することも可能です。電力そのものは分配できませんが、バーチャルPPAで得た環境価値であれば、そのような分配・調整ができるメリットがあります。
RECの入手が安定する
REC(グリーン電力証書)の長期間にわたっての安定的な入手が可能になる点も、バーチャルPPAのメリットです。REC(グリーン電力証書)とは、グリーン電力(再生可能エネルギーで発電した電力)の使用・購入により、太陽光・風力・地熱などの発電設備・維持・拡大に貢献したことの証明書を指します。
バーチャルPPAの導入を継続すれば、10〜20年はRECが付与されるため、長期間にわたって再エネ利用による環境への配慮をしていることの証明になります。
一方で、非FIT非化石証書(再エネ指定)とは、RECとは異なり、発電事業者が政府のFIT(固定価格買取制度)や化石燃料を利用しない環境で発電した電力の証明として発行される証書です。この証書は、RECと同様に再生可能エネルギーの使用を証明するものの、非FIT非化石証書は、政府補助金や化石燃料の利用がないことを明確に証明する点でRECと差別化されます。
バーチャルPPAのデメリットと課題

多大なメリットをもたらすバーチャルPPAですが、デメリットともいえる点も決してゼロではありません。バーチャルPPAのデメリット・課題を説明します。
購入者の負担
先述したとおり、バーチャルPPAは市場価格と契約価格(固定価格)の差額を購入者が精算する手順ですが、この仕組みが購入者の負担になる恐れがあります。この精算方法であれば発電事業者にとっては安定した収益が見込めるメリットがありますが、市場価格が下落した場合、購入者に負担になる可能性もあるのです。
下落した場合に起こるパターンが、電力購入者による一方的な発電事業者への差額の補填です。再生可能エネルギー発電設備の種類によっては、電力供給過多が起きて市場の価値が急落する可能性もあり、この場合は購入者の方に負担がかかります。
会計処理
会計処理が複雑になってしまうことも、バーチャルPPAのデメリットです。バーチャルPPAは通常の商品のように決まった金額ではなく変動する可能性も高いため、会計処理上、複雑になる恐れがあります。
バーチャルPPA導入の際は、税理・会計に関する知識・スキルを持った人材の確保、専門の会計士や顧問に依頼するとよいでしょう。
バーチャルPPAの事例
バーチャルPPAを企業はどのように導入しているのか、2つの企業の事例を紹介します。
清水建設株式会社
清和綜合建物株式会社(東京都千代田区 代表取締役社長 大串桂一郎 以下「清和綜合建物」)、清水建設株式会社(東京都中央区 代表取締役社長 井上和幸 以下「清水建設」)、清水建設100%出資の小売電気事業子会社スマートエコエナジー株式会社(東京都中央区 代表取締役 長澤幹央 以下「スマートエコエナジー」)が10月23日に締結した「オフサイトコーポレートPPAサービス契約」に基づき、スマートエコエナジーが清和綜合建物所有のオフィスビル3棟へ再生可能エネルギーを11月より供給することとなりましたのでお知らせ致します。
PPAは「Power Purchase Agreement」の略で、長期・固定価格での電力購入契約を意味し、オフサイトは需要家の敷地外の遠隔地からの電力調達を意味します。今回のスキームでは、スマートエコエナジーが、千葉県印西市の清水建設の太陽光発電所で創出した太陽光電力と、非化石証書充当によるCO2フリーの実質再エネ電力を合わせて、清和綜合建物が所有する3棟のオフィスビルに20年に亘り安定的に供給します。供給量は年間約245万kWhで、3棟の使用電力は全量RE100対応になります。これによるCO2排出量の削減効果は年間約1,125トンになります。
引続き、清和綜合建物と清水建設、スマートエコエナジーの3社は、再生可能エネルギーの取引を通じ、脱炭素化と持続可能な社会の実現に寄与して参ります。
引用:オフサイトコーポレートPPAの活用による再生可能エネルギー由来の電力導入について|2023年11月1日|清水建設株式会社
東急建設株式会社
東急建設株式会社(代表取締役社長:寺田光宏)と株式会社クリーンエナジーコネクト(代表取締役:内田鉄平)は、国内初となる建設現場を対象としたバーチャルPPAサービス契約を締結しました。これにより、東急建設の建設現場における使用電力に対して、追加性※1のある再生可能エネルギーの環境価値がクリーンエナジーコネクトから長期で提供されます。
※1 追加性:企業の選択した調達方法が再生可能エネルギーへの投資を促進し、化石燃料の代替に繋がっていることを表すもので、再生可能エネルギーの調達に積極的な企業の中で、重要視されています。
引用:国内初となる 建設現場を対象としたバーチャルPPAサービス契約を締結|2022年12月22日|東急建設株式会社
まとめ
バーチャルPPAは、電力そのものではなく、再生可能エネルギーにより発電された電力の「環境価値」を購入する手段です。バーチャルPPAを購入すれば、環境に配慮した活動を行っている証明にもなり、企業イメージのブランディングにも貢献します。
通常の電力契約を継続しつつ、手間がなく環境への貢献ができるなどメリットの多いバーチャルPPAですが、会計が複雑などのデメリットもあります。本当に自社に適した手段であるかどうか、メリットとデメリット、特徴をしっかりと把握してから、導入するかどうかを決めることが大事です。
建設業界では、入札段階や工事成績評点で施工時や竣工後の建築物においてCO2排出量の削減が評価され、加点につながる動きが生じています。また、建設会社からCO2排出量を開示し削減方針を示さないと、発注者であるデベロッパーから施工者として選ばれにくくなる状況も起きており、建設会社にとってCO2排出量の管理・削減は喫緊の課題です。
リバスタでは建設業界のCO2対策の支援を行っております。新しいクラウドサービス「TansoMiru」(タンソミル)は、建設業に特化したCO2排出量の算出・現場単位の可視化が可能です。 ぜひこの機会にサービス内容をご確認ください。

この記事の監修

リバスタ編集部
「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、
建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。
「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、
建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。
本ウェブサイトを利用される方は、必ず下記に規定する免責事項をご確認ください。
本サイトご利用の場合には、本免責事項に同意されたものとみなさせていただきます。当社は、当サイトに情報を掲載するにあたり、その内容につき細心の注意を払っておりますが、情報の内容が正確であるかどうか、最新のものであるかどうか、安全なものであるか等について保証をするものではなく、何らの責任を負うものではありません。
また、当サイト並びに当サイトからのリンク等で移動したサイトのご利用により、万一、ご利用者様に何らかの不都合や損害が発生したとしても、当社は何らの責任を負うものではありません。


