

潮力発電とは?仕組みや特徴、メリットについて解説
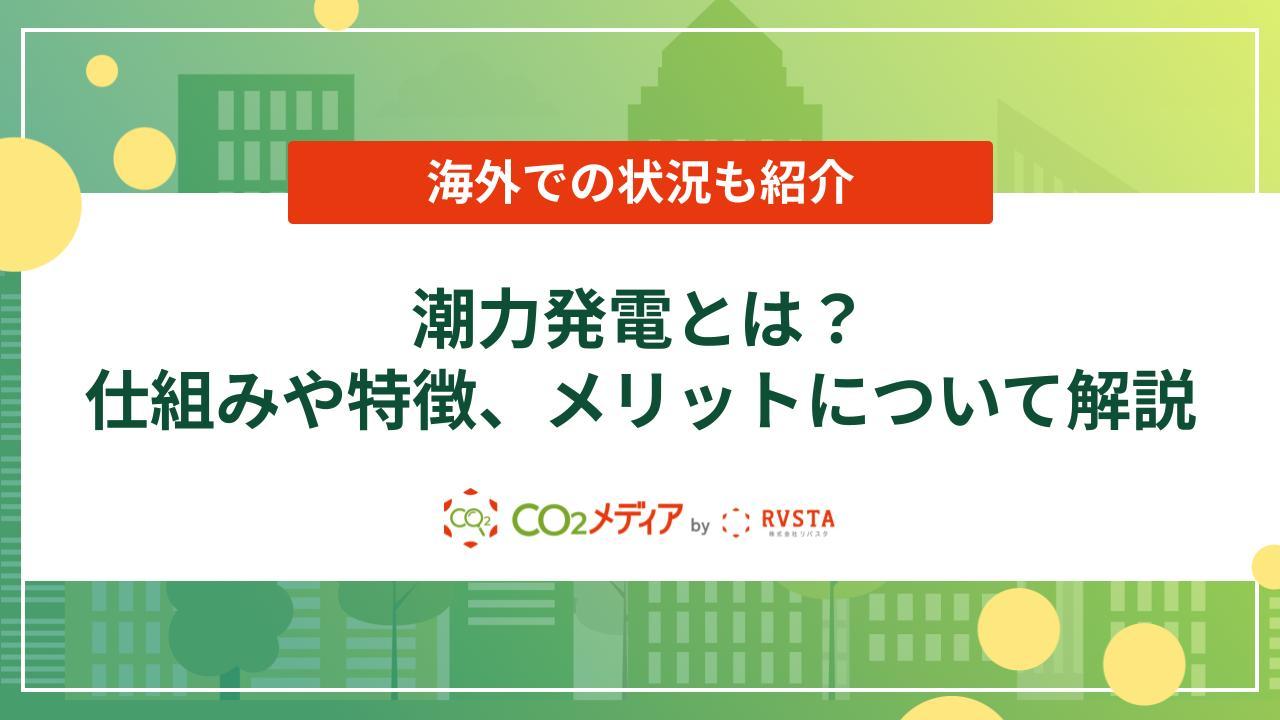
潮力発電は潮の満ち引きのエネルギーを発電に変えるシステムで、再生可能エネルギーの中でも、特に注目を集めている発電方法です。
本記事では、建設業界の方向けに潮力発電の仕組みからメリット、課題、日本や海外の活用状況について解説しますので、ぜひ参考にしてください。
潮力発電とは?

潮力発電とは潮の満ち引きが持つ運動エネルギーを電力に変える発電方法です。近年、再生可能エネルギーが注目され、世界中で利用するようになってきました。
中でも、日本のように周りに海がある海洋国では、1年中安定して供給できる潮力発電が注目されています。潮力発電の仕組みや導入された背景について他の再生可能エネルギーと比べると認知度は依然として低いですが、今後伸びてくる発電方法になるため、解説していきます。
潮力発電の仕組み
潮力発電は、海の潮の満ち引きを活用して発電する方法です。潮汐の周期的な動きによって生み出される潮位差は、発電に活用できるエネルギーです。その時に生じるエネルギーを利用して羽根の付いたタービンを回し、発電するシステムで、潮力発電は大きく分けて「潮流発電」と「潮汐力発電」の2つがあります。
潮流発電
潮流そのものを利用する「潮流発電」は、海の水平方向の流れを利用して発電します。潮流とは、月と太陽の引力がもたらす海水の水平な流れのことであり、潮流は周期的に変動しています。海峡などのように狭まったところでは潮流の流速は早くなるため、専用のタービンを設置することで発電を行うことが可能です。
潮汐力発電
一方、潮の干満差を利用する「潮汐力発電」は、垂直方向の干満差により得られる位置エネルギーを活用して発電を行います。具体的には、潮位差が大きい湾や河口の入り口などに防波堤や水門などを建設して湾と海を仕切り、防波堤や水門の海底付近に潮の流水口と羽根の付いたタービンを設置します。
満潮時には貯水し、干潮時に水門を開放して水を放出することでタービンを回転させて発電することが可能です。月と太陽の引力によって地球の海面は12~24時間周期で上下運動しており、潮汐は周期的な現象のため、干潮と満潮の時刻を予測できれば発電計画も立てやすいです。
潮力発電の導入の背景
潮力発電が注目されるようになった背景には、地球温暖化対策の政策として、ヨーロッパ諸国などで再生可能エネルギーの利用を積極的に推し進めているということがあります。潮力発電を含む海洋エネルギーもその中の一つで、1966年にフランスのランス川河口に初めて導入されました。
特に、潮力発電は同じ自然エネルギーである太陽や風力よりも天候などの条件に左右されることが少なく、潮の満ち引きは定期的に訪れます。そのため、発電設備のコントロールがしやすく、安定して発電することが可能です。現在は米国を筆頭に、世界中で潮力発電をはじめとした海洋エネルギーの開発が活発化しています。
日本では、2030年度において2013年度比46%減の温室効果ガス排出量削減目標及び、2050年のカーボンニュートラル実現目標達成のためには再生可能エネルギーの導入推進が欠かせなくなりました。
そのため、様々な発電方法が模索されており、日本は排他的経済水域が世界第6位という海洋国であるということから海洋再生可能エネルギーの導入が注目されています。海洋エネルギーを利用した発電方法の中でも一年中安定した発電が見込める潮力発電は広く導入されることが期待されています。
潮力発電のメリット

潮力発電は、定期的な潮の満ち引き、地球や月の周期的な動き、潮流のスピードや水量などから発電量予測の計算やコントロールがしやすいというメリットがあります。そのため、電気の安定供給にも大いに期待できます。特に、四方を海で囲まれている日本は、潮力発電の導入に関して大変有利で利用しやすい環境が揃っています。
また、発電設備のタービンを水深5mに設置して発電するため、再生可能エネルギーの中でも太陽光や風力と比較して天候に左右されません。海洋で発生する自然の力を活用するため運用コストも低く、燃料も必要ないため、環境に対しても負荷が少なく済みます。有害物質を排出しないため、原子力発電や火力発電と比べて環境汚染のリスクも低いです。
潮力発電のデメリットと課題
潮力発電の設備は海中に設置するため、海水の塩分や貝などの付着によって機材の早期劣化が懸念されており、設備に対しての対策やメンテナンスに追加のコストが発生します。耐用年数が5~10年と短いため、コストパフォーマンスが悪いという指摘があるのも事実です。さらに、潮力発電は他の再生可能エネルギー設備と比較すると建設コストが高いと言われています。
また、潮力発電を行うためには、適切な潮流が得られるエリアが必要になります。タービンの羽根の強度に適しているかどうかや、漁業権、航路といった点も含めると、設置できるエリアは限定されてしまうといった課題もあります。このような制約により、世界全体の潮流発電のポテンシャルは3,000GWですが、発電に適しているエリアは全体の3%にとどまっています。
さらに、規模を大きくしすぎてしまうと海洋の生態系に影響を及ぼす可能性も高まります。特に、タービンの羽は海洋動物にダメージを与える危険性があり、カナダで37年稼働していた潮汐発電所では水産海洋省の調査で魚への影響が確認されました。影響が確認されたことにより、発電所は2022年に閉鎖され、潮力発電の環境への影響を慎重に考える必要性が高まったのです。
潮力発電の日本の実証実験
日本の潮力発電の取り組みは、他の再生可能エネルギーやヨーロッパ諸国の潮力発電開発から遅れをとっていました。しかし、近年では、大規模な潮力発電の開発に力を入れ始めています。その場所というのが、長崎県の五島列島です。
長崎県の五島列島
2014年より実施された「潮流発電技術実用化推進事業」において、国の海洋再生可能エネルギー実証地として選定された長崎県五島市久賀島沖での取り組みと調査データが環境省より公開されました。
また、2022年1月には、「令和4年度潮流発電による地域の脱炭素化モデル構築事業」で、長崎県五島市沖奈瑠瀬が国内初の商用スケールの大型潮流発電の実証実験地として採択されました。
すでに初期段階の実験を終え、大型発電機の設計に取り組んでおり、2024年度に九州電力の子会社「九電みらいエナジー」による国内初導入を予定しています。
海に囲まれた日本での活用に期待が高い
太陽光発電や風力発電などの導入を進める中で、日本の国土は傾斜が急で平野が乏しく、火山や丘陵などを含めた山地は約75%ほどです。そのため、陸上において発電設備を設置できるスペースは限定されています。
しかし、同じ島国で四方を海に囲まれており豊富な海洋エネルギーが得られるイギリスは海洋エネルギー開発に積極的に着手しています。同じ地理条件を持つ日本でも海洋エネルギーが得られる場所は豊富にあり、海峡・瀬戸を中心とした沿岸地に潮力発電の適地が存在しています。また、日本政府は2050年までに潮流と海流発電を合わせて200億kWh/年を達成することを展望しており、ポテンシャルの高い潮力発電への大きな期待が寄せられています。
海外での潮力発電の状況

日本の潮力発電がヨーロッパ諸国に比べて遅れを取っていることについて解説しましたが、海外での潮力発電の状況はどうなのでしょうか。世界各地の潮力発電の先進的な取り組みを中心に、イギリス、韓国、フランス、カナダの4か国を例に挙げて解説していきます。
イギリス
英北部スコットランドで、潮の流れを利用した潮力発電が本格的に始動する見通しとなった。潮力発電事業を専門とする英アトランティス・リソーシズは9月中旬、計画中の世界最大規模の発電施設で用いる発電用タービンの組み立てを完了。近く海底に設置し、年内にも送電を始める予定だ。再生可能エネルギーの新たな電力供給源である潮力が、実験段階から商用化へと大きく前進する。
英アトランティスが公開した潮力発電用タービン(英北部スコットランド)
アトランティスはこのほど、1基あたり1.5メガワットの発電能力を持つ4つのタービンの組み立てを完了し、業界関係者らに公開した。重量は1基あたり約200トンで、高さが15メートル、羽根の直径は18メートルに達する。このタービンを海底に設置し、潮の満ち引きによる潮流を利用して回転させることで発電する仕組みだ。
韓国
韓国では、「始華湖潮汐発電所」が2011年度から始華湖と西海の間で稼働し始めました。満ち潮の時だけ発電が可能な漲潮式発電方式で1日2回、4時間ずつ発電機を稼働させています。引き潮の時は、始華湖の海水面の高さが3m下がった状態で水門を塞いでいます。
一方、満ち潮が始まれば潮差が約2mになった時に水門を開き、流れ込む海水が直径7.5m・重さ53tのプロペラを作動させて発電するという原理です。この発電設備は10基合計で254MWの出力を持ち、建設当時で世界最大級の規模を誇ります。年間の発電量も5億4400万kWhに達し、韓国最大の昭陽江多目的ダムの1.56倍です。
今後さらに干満差が大きい海域を中心に大規模な潮力発電所を複数設置予定で、開発が活発化しています。
参照:世界最大級の潮力発電所 京畿道の始華湖…11月に着工|在日本大韓民国民団
フランス
1966年にフランス北部のブルターニュ地方のサン・マロ近郊に世界初の潮力発電所「ランス潮汐発電所」が完成しました。この発電所の最大定格出力は24万kW、年間発電量は6億kWhにのぼります。
ランス川の河口に位置するこの発電所は、現在も稼働しており、フランスの電気消費量の0.12%を供給。歴史的な背景を持ちながらも、50年近い長期間の運転に問題がなく、持続可能なエネルギー供給源として証明し続けています。
また、2014年には海底に設置したタービンを海流の力で回転させ発電する技術の試験を開始し、海流は1.75m/s以上、水深は25〜50mの海底に設置されています。
この基準は、船舶の航行や漁業活動を妨害せず、また波力でタービンが過度な疲労を起こさない深さを考慮したもので、潮力の強いフランスのブルターニュとノルマンディーの沿岸が有望視されています。
参照:11月26日 世界初の潮力発電所が完成(1966年)|現代ビジネス
カナダ
カナダ東部の沿岸では、潮の流れを利用して電気をつくり出す「潮力発電」が本格的に始動し、500世帯分の電力の供給を開始しました。
中部電力と川崎汽船が世界最大級の干満差を誇る、東海岸のノバスコシア州とニューブランズウィック州の間に位置するファンディ湾にて実施されるイシュカ・タパ潮流発電事業に参画しており、日本企業が海外において初めて参画する潮流発電事業です。
ファンディ湾は潮の流れが速いことで知られており、潮位は通常でも20mを超えます。タービンはフランスの海軍造船企業の子会社オープンハイドロが設計・製造したもので、2023年に1基目の運転を開始し、今後設置予定の2基目と合わせると、石炭2000tによる発電量に匹敵する電気を生み出せます。
参照:カナダ、潮力発電が本格始動 500世帯分を供給|AFPBB News
まとめ
潮力発電は、地球にやさしい再生可能エネルギーの一つとして世界中で注目されている発電方法です。潮力発電といっても、「潮流発電」と「潮汐力発電」の2つのタイプがあります。同じ潮力を活用した発電方法でも仕組みは若干異なりますが、海洋国の日本に最適なシステムのため、建設業界でも今後の活用に期待できるでしょう。
一方で、潮流発電にはメリットもあればデメリットも存在します。しかし、有害物質を排出しない潮力発電は、未来を思い遣った再生可能エネルギーとして積極的に取り入れていく必要があります。
建設業界では、入札段階や工事成績評点で施工時や竣工後の建築物においてCO2排出量の削減が評価され、加点につながる動きが生じています。また、建設会社からCO2排出量を開示し削減方針を示さないと、発注者であるデベロッパーから施工者として選ばれにくくなる状況も起きており、建設会社にとってCO2排出量の管理・削減は喫緊の課題です。
リバスタでは建設業界のCO2対策の支援を行っております。新しいクラウドサービス「TansoMiru」(タンソミル)は、建設業に特化したCO2排出量の算出・現場単位の可視化が可能です。 ぜひこの機会にサービス内容をご確認ください。

この記事の監修

リバスタ編集部
「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、
建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。
「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、
建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。
本ウェブサイトを利用される方は、必ず下記に規定する免責事項をご確認ください。
本サイトご利用の場合には、本免責事項に同意されたものとみなさせていただきます。当社は、当サイトに情報を掲載するにあたり、その内容につき細心の注意を払っておりますが、情報の内容が正確であるかどうか、最新のものであるかどうか、安全なものであるか等について保証をするものではなく、何らの責任を負うものではありません。
また、当サイト並びに当サイトからのリンク等で移動したサイトのご利用により、万一、ご利用者様に何らかの不都合や損害が発生したとしても、当社は何らの責任を負うものではありません。


