
建設における副産物の処理を行う際には、「コブリス」を使うことが求められます。コブリスは建設副産物のリサイクルを推進するために用いられる、専用のシステム・ツールです。
建設業ではこのコブリスを上手に活用することが重要とされています。
本記事では、「コブリスとは何か?」という基本から、メリットや使い方を解説します。
コブリスとは何か?

コブリスは建設業や処理業を行う人たちにとって、重要なシステムとなります。まずはどのようなシステムかを把握し、基本的な使用方法を知ることが最初のステップです。以下では、コブリスの基本について解説します。
コブリスとは「建設副産物情報交換システム」のこと
コブリスとは、国土交通省が提供する「建設副産物情報交換システム」を指します。「Construction Byproducts Resource Information interchange System」の頭文字を取って、「COBRIS(コブリス)」と呼ばれています。
建設副産物情報交換システムは、工事の発注者、廃棄物排出事業者、処理業者の間でリアルタイムに情報をやり取りし、建設副産物の需給調整、適正な処理の促進、リサイクルの推進を目指すシステムです。
また、建設リサイクル法に基づく書類作成を電算上ですることによって、記入者の負担を軽減することができます。主に工事発注者、排出業者、処理業者を対象としたシステムであり、関連事業者にはコブリスの使用が推奨されています。
建築副産物に含まれる種類
コブリスは建設副産物のリサイクルおよび適正な処理を行うためのシステムです。建設副産物とは、建設工事で副次的に発生した物品をすべて含んでおり、以下の副生成物がシステムに含まれています。
| 再生資源材利用 | 対象副産物を材料とする再生資源を再生資源化施設より搬入する場合に適用される ・コンクリート塊 ・アスファルト・コンクリート塊 ・建設発生木材 ・建設汚泥 ・建設混合廃棄物 など |
| 建設副産物搬出 | 対象副産物を再資源化施設または最終処分場に搬出する場合に適用される ・コンクリート塊 ・アスファルト・コンクリート塊 ・建設発生木材 ・建設汚泥 ・建設混合廃棄物 など |
コブリスとクレダスの違いについて
クレダスは、国土交通省が運営する建設リサイクル統合システムで、平成14年から利用されています。「再生資源利用計画書・実施書」などの作成や入力、集計を支援します。また、建設副産物実態調査の報告にも活用されています。しかし、クレダスは平成29年に廃止されました。
一方でコブリスは、日本建設情報総合センターが運営する建設副産物情報交換システムで、クレダス同様の機能が含まれています。しかし、クレダスは国が用意するシステムをダウンロードして使用していましたが、コブリスはオンライン上で利用できます。
コブリスの主な機能

建設副産物情報交換システムであるコブリスには、さまざまな機能が搭載されています。各機能の詳細を確認し、日々の業務に活用できれば業務効率のアップが期待できます。以下では、コブリスの主な機能について解説します。
建設副産物の処分先と再生資材の購入先を検索できる
コブリスは登録された情報が受発注者のみならず、国の機関でも活用することができるため、建設副産物の処分先と再生資材の購入先についての情報を、容易に検索できる機能があります。この検索機能を使うことで、工事現場から施設までの最多ルートなどを把握することができ、業務効率化にも繋がります。
建設リサイクル法に基づいた帳簿を作成・保存できる
建築副産物情報交換システムを利用することで、建設リサイクル法に基づいた帳票の電子化が可能です。そのため、コブリスでは建設リサイクル法に基づいた帳簿を、一から作成して保存までを終わらせられます。電子データとして帳簿を保存できるため、その後の情報源としても活用できます。
データのチェックも容易に行えるので、様々な事業で情報を役立てられるでしょう。このように、コブリスを活用すると精度の高い書類作成が行えるため、自社の業務改善にもつながります。
リアルタイムの情報をインターネットから収集できる
コブリスで検索できる情報は、リアルタイムでインターネットから収集可能です。そのため深夜・早朝といった時間帯に関係なく、いつでも必要な情報を確保できることも特徴です。
インターネット環境さえあればどこからでもコブリスにアクセスできるので、必要なときに必要な情報が得られます。
工事情報の登録や更新などが地図データを使って利用できる
コブリスでは、工事情報の登録や更新などが地図データを使って容易に利用できます。工事発注者・請負会社情報といった工事情報の概要以外にも、地図検索機能により、地図上から工事情報の登録が行えるため、スムーズに多くの情報を確保できます。
また、重複している工事データなどは、検索して削除する機能もあります。
処理事業者は自社の存在をコブリスで宣伝できる
廃棄物の収集運搬や処分を行う事業者は、各都道府県知事の許可を得たうえで対応可能な品目を決定します。このため、対応品目が把握しづらく、処理事業者を利用したいけれどどの業者に依頼すべきかわからないというケースも多いです。
その点、コブリスでは処理事業者も情報を登録し、PR欄を使って自社の宣伝が行えるため、コブリスを確認しながら処理事業者を選定することも可能です。
コブリスを使うメリットとは?

コブリスを利用すると、さまざまなメリットが得られます。このメリットにより作業効率が増し、コストダウンが期待できます。以下では、コブリスを使う際の主なメリットについて解説します。
設計や積算の際の参考になる
コブリスは、工事データを把握できるため、工事発注者にとっては、適切な設計・積算の支援にも役立ちます。工事発注者はあらゆる情報を確認したうえで、設計や積算を実施します。その際にコブリスを利用することで、必要な情報の確認・比較・検討などの作業を短時間で済ませられるでしょう。
施工計画や作業計画の流れを構築しやすくなる
排出事業者は、施工計画や作業計画の流れを構築しやすくなる点もコブリスのメリットです。施工計画や作業計画の立案にも、多くの情報とそれを軸にした話し合いが必要になります。情報収集の段階でつまずくと、なかなか具体的な話し合いに進めない可能性もあるでしょう。
そこでコブリスを活用し、段取りよく進められる環境の構築にメリットがあります。
信頼できる処理業者と出会いやすくなる
コブリスは工事発注者や排出業者だけでなく、処理業者も利用できるシステムです。そのためコブリスをきっかけにして、信頼できる処理業者と出会える可能性もあります。コブリスのPR欄で処理業者を見つけられれば、別途業者探しに時間を割く必要がなくなります。
結果的に事業全体の時間を短縮し、スムーズな成果の獲得につなげられるでしょう。
工事現場に近い処理施設や搬出先ルートを簡単に検索できる
コブリスを使うことで、工事現場に近い処理施設や搬出先ルートを容易に検索できます。最短経路を把握できるため、より効率的な事業推進ができるでしょう。また、工事現場から施設までのルート検索も可能なため、迷うことなく現場への移動が可能です。
このように、コブリスには所要時間の計算機能も備わっているため、計画的に業務を行えることもメリットです。
帳票の集計機能が使える
コブリスには登録されている工事情報を集計できる機能も備わっています。工事情報の収集と確認の手間が削減されるため、さまざまな事業にメリットを与えられるでしょう。
さらに、自社が登録した情報の集計結果をファイルでダウンロード可能であるため、国土交通省が実施する「建設副産物実態調査」に対応した書類も作成可能です。
コブリスを使う方法・手順

コブリスを利用する際には途中でわからないことが出ないように、いくつかの手順に沿って登録を進める必要があります。以下では、コブリスを使うための方法・手順を解説します。
建設副産物情報センターにアクセスして「システム利用申請方法」を選択する
コブリスを利用するには、まず「建設副産物情報センター」にアクセスします。その後画面にある「ユーザー情報変更・申込」をクリックし、サービスを利用するための登録準備を進めます。「システム利用申請方法」を選択することで、新規での登録が可能です。
「排出事業者・工事施工会社」から「新規ユーザー登録」を選ぶ
コブリスのサイトで「ユーザー情報変更・申込」を選択したら、ユーザー区分である「発注者」「排出事業者」「処理業者」を選択します。その後、本サービスを利用するうえでの責任者のメールアドレスを登録します。
「建設副産物情報交換システム」にチェックを入れて情報を入力する
コブリスの登録を進めるには、そのまま「建設副産物情報交換システム」にチェックを入れます。その後、必要情報を入力して登録の準備を行いましょう。会社情報など必要事項を画面の指示に沿って入力します。
登録を終えたら「利用申請書」を印刷する
コブリスの利用登録を終えたら「利用申請書」の作成と登録を行います。コブリスを使うには書類の作成後に「利用申請書」を印刷し、日本建設情報総合センターに郵送する必要があります。日本建設情報総合センターのチェックを受けて問題がないことを確認されると、コブリスの使用が可能となります。
ユーザー区分によって利用申請書と一緒に送付する必要書類が変化するので、システムの指示の確認が必要です。
案内メールが届いていることを確認する
コブリスの利用申請書を郵送し、日本建設情報総合センターによるチェックが行われると案内メールが送付されます。メールは最初に登録したアドレスに送付されるため、迷惑メールに紛れていないか確認しておくとよいでしょう。案内メールのなかには、利用料金の請求書が添付されています。(輸送で届くこともあります)
コブリスのシステムを利用する料金は、発注者・排出事業者・処理業者といった区分で変わります。金額を確認したら所定の方法で入金し、日本建設情報総合センターが入金チェックを行います。問題がない場合には、システムのユーザーIDと初期パスワードがメールにて送付されるので確認しましょう。
発注者は無料でのお試しサービスを活用できる
工事の発注者に区分される業者は、コブリスを無料で利用できるお試しサービスの対象者となっています。上記の流れにおいて入金が不要となるため、スムーズにサービスの使い心地をチェックできます。無料お試しの期間は、最長6ヶ月となっています。
その間にコブリスの使い方や有効利用する方法を見つけられれば、有料になっても無駄なく各機能を活用できるでしょう。
コブリスを使う際の注意点
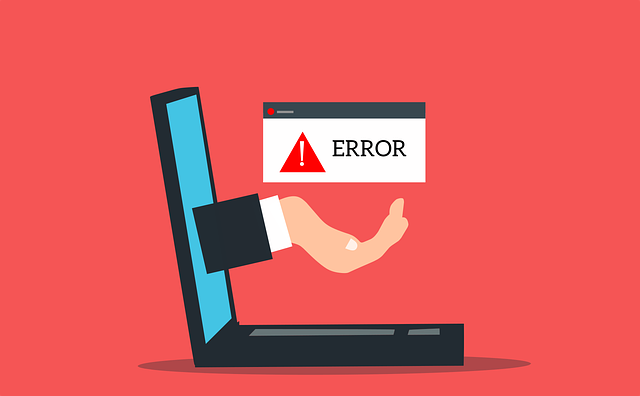
コブリスを利用する際には、いくつかの注意点があります。使用中にトラブルが発生する可能性もありますので、以下を参考にコブリスを使う際の注意点を確認しておきましょう。
年度ごとに更新手続きが求められる
コブリスの利用時には、年度ごとに更新手続きをしなければなりません。1度登録して終わりではなく、その後も利用する際には継続のための更新手続きが必要になります。年度ごとの更新手続きを怠ると、コブリスの機能が使えなくなるため注意が必要です。
そのため更新のタイミングをチェックして、事前に準備を進めておくのがポイントです。コブリスのシステム利用期限は、ユーザーIDを取得した日を軸に、当該年度の3月31日までとなっています。この期間までに更新手続きを行わないと利用停止の処理が進んでしまうため、こちらも注意が必要です。
利用料金は請求書を受理した日から30日以内に支払う
コブリスの利用時に必要となる利用料金は、請求書を受理した日から30日以内に支払う必要があります。そのため請求書を受理したら、そのまま放置せず速やかに支払うことがおすすめです。
支払い忘れを防止できるようにコブリスの担当者を設定するなど、責任者を明確にすることがポイントです。
不明点は専門家に確認するのもおすすめ
未経験でコブリスを利用すると、様々な不明点が出てくると思われます。基本的な使い方や有効利用につながる方法がわからない場合、登録してもそのシステムを活かしきれないケースが懸念されるので、コブリスを利用する際には事前に専門家やコンサルタントなどに相談し、利用方法を確立しておくのもおすすめです。
建設業をサポートするコンサルティング業者など専門家に依頼することで、コブリスの利用方法や関連するシステム制度に関する情報をスムーズに確保できる可能性があります。そのため、長期的な運用を見据えて専門家にサポートを依頼することがおすすめです。
まとめ
コブリスは国土交通省が提供する「建設副産物情報交換システム」として、工事発注者・排出業者・処理業者などが利用しています。システムの利便性は高く、建設業においてもさまざまなシーンで活用できるでしょう。しかし、コブリスを有効利用するためにはそのメリットと使い方を熟知し、自社の事業に落とし込む必要があります。
まずは「コブリスとは何か?」という基本を把握しつつ、この機会にコブリスの基本と使い方を確認し、導入後の利用方法を考えてみてはいかがでしょうか。
株式会社リバスタは、電子マニフェストサービス「e-reverse.com」、建設現場施工管理サービス「Buildee」、建設現場ICT機器ソリューション「BANKEN」などのさまざまなサービスを提供しています。これらの機能も建設業で多いに役立つため、この機会にコブリスと合わせてぜひ導入をご検討ください。

この記事の監修
リバスタ編集部
「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。











