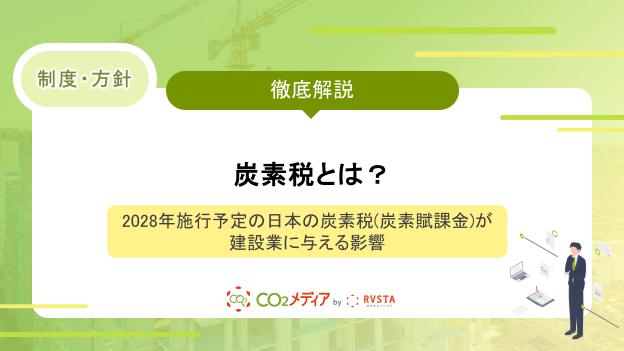
温室効果ガスの排出量に応じて課税される税金を炭素税と呼びますが、2028年には炭素税の一種である炭素賦課金が施行予定であり、建設業界にとって大きな影響を与える可能性があります。炭素税も炭素賦課金も化石燃料使用に伴い支払いが生じるため、制度上の違いはありますが本質的には同じです。この炭素賦課金が導入されることによって、建設機械の運用コスト増加や電力料金の上昇などさまざまな面で対策が必要です。このように、炭素税の導入が徐々に進んでいます。
本記事では、炭素税が建設業界に与える影響を解説しています。また、炭素税を契機とした新たなビジネスモデルや今後の戦略も解説しているため、炭素税導入に向けた検討が必要な方は参照してみてください。
目次
炭素税とは何か?

炭素税は環境税の一種であり、温室効果ガスの排出量に応じてかけられる税金です。基本的に排出枠取引とセットで運用され、排出に価格付けを行う政策であるカーボンプライシングの一環です。この炭素税の基本的な仕組みや建設業界に与える影響、課題と対応策を解説します。
炭素税の基本的な仕組みと目的
炭素税は地球温暖化対策を目的とした税制度で、化石燃料の使用に伴うCO2排出量に課税することで、温室効果ガスの削減を促進する仕組みです。
炭素税は一部ですでに導入されており、石油や石炭などの化石燃料から発生するCO2が課税対象で、排出量1トンあたり289円の基準で税率が設定されています。燃料の使用量に応じて税額が決まる仕組みで、既存の石油石炭税に上乗せする形で徴収されます。
このため、燃料費の増加により、エネルギー効率の改善や再生可能エネルギーへの転換が経済的に有利になるため、市場メカニズムを通じた脱炭素が期待できます。
炭素税が建設業界に与える具体的な影響
建設業では事業活動全般においてCO2の排出が避けられないため、炭素税の影響は特に深刻です。直接的な影響として建設機械の運用コスト増加が挙げられます。
ブルドーザーやショベルカーなどの重機は大量の軽油を消費するため、炭素税によるガソリン価格上昇は現場作業費を押し上げます。また、建設資材の運搬も輸送費の増加が避けられず、プロジェクト全体のコストに影響を与えます。
日本の電力供給が化石燃料に依存していることから、炭素税の本格導入により電力料金の上昇も懸念されます。電力料金の上昇により、電動工具の使用や現場照明、事務所運営など、電力を必要とする幅広い業務でコスト増が予想されます。
建設資材自体の価格変動も重要な要素です。セメントや鉄鋼などの製造過程で多くのCO2を排出する資材は、炭素税の影響で価格上昇が見込まれます。
炭素税導入による建設業界の課題と対応策
炭素税導入に伴う建設業界の課題は、建設機械から排出される大量のCO2です。現在使用されている重機の多くは化石燃料に依存したエンジンを搭載しており、作業の性質上、排出量削減が困難な状況にあります。
課題への対応として、まず建設機械の燃費効率向上が重要な取り組みとなり得ます。エンジンの改良やハイブリッド化により、同じ作業量でも燃料消費を抑制できる省エネ型建設機械の導入が必要です。また、電動化技術の進歩により、小型機械から段階的に電動仕様への転換も検討されています。
現場運営全体での脱炭素も必要です。太陽光発電システムの設置や風力発電の活用など、再生可能エネルギーの導入により現場での電力需要を賄う取り組みが注目されています。
2028年の炭素賦課金導入に向けた建設業界の準備

2028年の炭素賦課金導入に向けて建設業界として準備していかなければなりません。準備にあたって、炭素賦課金導入スケジュールと政府の方針、今から取り組むべき対策、補助金や支援制度の活用をそれぞれ詳しく解説します。
炭素賦課金導入スケジュールと政府の方針
2028年度からの炭素賦課金導入に向けて、建設業界では今から戦略的な準備が不可欠となっている状況です。これにより、化石燃料輸入企業に対して炭素賦課金が義務化される予定です。これらの税制度の変更により、エネルギーコストの上昇を通じて建設業界全体に波及効果をもたらすことが予想されます。
具体的には次の課税方法が検討されています。
| 工程 | 課税方法 |
| 上流課税 | 採取時点、輸入時点で課税 |
| 中流課税 | 製造所から出荷する時点で課税 |
| 下流課税 | 工場、オフィス、家庭等へ供給する時点で課税 |
| 最下流課税 | 最終製品・サービスが最終消費者に供給される時点で課税 |
現在の準備期間は、業界にとって重要な転換点です。炭素賦課金の導入により、ガソリンや軽油などの燃料価格が上昇するため、建設会社は早期の対応策の検討が求められています。
建設業界が今から取り組むべき対策
2028年の炭素賦課金導入を控え、建設業界で今から着手するべき対策を紹介します。まず基盤となるのは排出量の可視化で、現場ごとのCO2排出量を正確に把握し、削減目標を設定する必要があります。
省エネ設備の導入と再生可能エネルギーの活用は、即効性があり効果的です。現場事務所への太陽光パネル設置や、高効率LED照明の採用により、電力由来のCO2排出を大幅に削減できます。また、エネルギー管理システムの導入により、無駄な電力消費を抑制する取り組みも重要です。
さらに、従来のディーゼルエンジンに代わり、バイオマス燃料や水素エンジンの使用原則化が国土交通省により進められています。
炭素税対策における補助金や支援制度の活用
炭素税対策において、建設業界は政府や自治体が提供するさまざまな補助金・支援制度を有効活用することで、初期投資負担を軽減しながら脱炭素を進めることができます。
例えば、再生可能エネルギー分野では、太陽光発電設備などの導入に対する課税標準の特例措置が適用されます。特例措置により固定資産税の負担軽減が図られ、建設現場や事業所への再生可能エネルギー設備導入のハードルが下がります。
資金調達面では、環境・エネルギー対策資金による融資制度が重要な支援策です。融資制度は非化石エネルギー設備の導入に特化した低利融資で、省エネ型建設機械の購入や電動化設備の導入に活用できます。
炭素税導入による建設業界のコスト構造の変化

炭素税導入によって建設業界ではコスト構造に次の変化が起こる可能性があります。
- 建設資材の価格変動と影響
- 建設機械の運用コストの増加と対策
- 建設プロジェクト全体のコスト管理の重要性
それぞれの変化を詳しくみていきましょう。
建設資材の価格変動と影響
政府が掲げる2030年までのCO2削減目標46%達成に向けた取り組みの中で、エネルギー集約型産業への影響が大きくなる懸念があります。セメントや粗鋼など建設に不可欠な資材では、製造過程で大量のエネルギーを消費するため、エネルギー価格が最大300%上昇する可能性が指摘されています。
中でもセメントの製造コスト上昇率約90%の予測は、建設業界にとって影響の大きい数字です。コンクリート構造物の建設費が大幅に増加することで、住宅建設から大型インフラプロジェクトまで、あらゆる分野でコストの見直しが必要です。
価格変動に対応するため、建設業界では代替材料の検討や設計手法の見直し、さらには顧客との価格転嫁交渉など、多角的な戦略が求められます。
出典:経済産業省/脱炭素化に伴うエネルギーコスト変化によるインパクト
建設機械の運用コストの増加と対策
炭素税の本格導入により、建設業界は建設機械の運用コスト増加の課題に直面します。建設機械の燃料費上昇は避けられず、価格転嫁が遅れれば企業収益に大きな打撃を与える可能性があります。
重機の稼働時間が長い大型工事では、燃料費の負担が従来の数倍に膨らむケースも想定されます。コスト増加の連鎖は市場全体に波及し、製品価格の高騰により顧客の発注意欲低下を招く恐れがあります。
対策として、電動建設機械の導入が急務です。初期投資は大きいものの、長期的には燃料コストの大幅削減が可能です。また、機械の稼働効率向上やメンテナンス最適化により、運用コストの抑制を図ることも重要です。
建設プロジェクト全体のコスト管理の重要性
炭素税導入により建設業界のコスト構造が大きく変化する中、プロジェクト全体を通じたコスト管理が企業の競争力を左右するより重要な要素となり得ます。従来の予算配分では対応できない新たなコスト増加に対応するため、戦略的な管理手法の確立が求められます。
各工程では次のような管理が必要です。
| 工程 | 必要な管理 |
| 実現可能性調査 | 炭素税影響の正確な予測 |
| 設計 | 環境配慮型設計の採用 |
| 入札 | 価格変動リスクの織り込み |
| 施工 | 省エネ運用の徹底 |
効果的なコスト管理により、限られた予算内で最適な資源配分を実現し、投資効果の最大化が可能です。例えば、省エネ型建設機械や再生可能エネルギー設備は初期費用が高額でも、長期的な燃料費削減により総コストを抑制できます。
炭素税導入に伴う建設業界の技術革新と新たなビジネスチャンス

炭素税導入による課題は多いものの、建設業界の技術革新の面では新たなビジネスチャンスとして捉えられる部分もあります。炭素税による変化を契機に新たなビジネスモデルの創出を検討できる可能性もあるため、ここで紹介する内容を自社の事業に参照してみてください。
低炭素型コンクリートの導入と効果
炭素税導入を契機に、建設業界の革新的な材料技術として注目されているのが低炭素型コンクリートです。低炭素型コンクリートは、ポルトランドセメントの55%以上を他の材料で置換することで定義されます。
低炭素型コンクリートは、製造時のCO2排出量を約50%削減でき、炭素税負担の大幅な軽減につながります。
現在の施工実績は、高炉スラグ微粉末を活用したプレキャスト製品の使用が主流です。鉄鋼副産物を有効活用することで、廃棄物処理問題の解決と建設材料の環境性能向上を同時に実現しています。
出典:国土交通省/低炭素型コンクリートの活用が全国的に拡大中!
電動建設機械の普及とメリット
炭素税導入を背景として、建設機械の電動化が急速に進展しており、電動化が業界に新たな技術革新とビジネス機会をもたらしています。
電動建設機械の特徴は、稼働時に排ガスを一切排出しないことです。さらに、電動モーターの特性により作業精度が大幅に向上し、従来のディーゼルエンジンでは困難だった繊細な操作が可能です。振動や騒音の軽減効果も大きく、都市部での工事における近隣への影響を最小限に抑えられます。
政府はGX建機の普及促進に積極的に取り組んでおり、公共工事での段階的使用推進を計画しています。また、GX建機を導入する事業者に対する補助金制度が整備されています。
炭素税を契機とした新たなビジネスモデルの創出
炭素税導入は建設業界にとって単なる負担増加ではなく、環境配慮の側面を超えて、新たな収益源と競争優位性の確立につながる戦略的機会として捉えられます。
このため、建設業界では、省エネ技術の革新的活用により従来の事業領域を拡大する可能性が広がっています。スマートビルディング技術やエネルギー効率最適化システムの導入により、建物のライフサイクル全体でのCO2削減を実現するソリューション提供も可能です。
カーボンニュートラル建設の分野では、建設プロセス全体でCO2排出をゼロにする技術とノウハウを確立することで、環境意識の高い顧客層を開拓できる可能性があります。
炭素税導入に向けた建設業界の戦略的対応

炭素税導入に向けて、中長期的な戦略策定や、炭素税による変化を踏まえて人材育成、組織体制の強化が求められます。
建設業界の戦略的対応をそれぞれ解説します。
炭素税導入に備えた中長期的な戦略の策定
炭素税導入を控えた建設業界は、短期的な対処ではなく、中長期的視点に基づく戦略策定が必要です。現在の企業活動が環境に与える影響を分析し、CO2排出削減に向けた具体的なロードマップを構築しなければなりません。
戦略策定で重要なのは、自社の事業領域や業種特有のニーズに応じた柔軟なアプローチです。住宅建設を主力とする企業と大型インフラを手がける企業では、CO2排出パターンや削減手法が大きく異なるため、画一的な対策では効果が限定的になりかねません。
実際の改善策として、省エネ型建設機械への段階的更新や、現場でのエネルギー管理システム導入などが考えられます。また、再生可能エネルギーへの転換は、現場での太陽光発電活用や事業所への風力発電導入など、多様な選択肢があります。これらの対策を導入することにより、運用効率の改善が期待できます。
炭素税に対応した人材育成と組織体制の強化
現状では、CO2の見える化や削減取り組み、脱炭素推進に必要な専門知識を持つ人材が圧倒的に不足しており、業界全体での能力向上が急務です。内閣府の調査結果が示すように、企業の約4割が「必要なノウハウ、人員が不足している」と回答している現実は深刻です。
建設業界でも、環境データの分析能力、省エネ技術の運用知識、法規制への対応力など、従来の建設技術とは異なる専門性が求められています。スキルのギャップを埋めるため、体系的な教育プログラムの構築と実務経験の蓄積が不可欠です。
効果的な脱炭素実現には、一企業内での取り組みから企業間連携、さらには官民一体となった大きな変革の流れを創出することが最も効率的です。
出典:内閣府/令和4年度年次経済報告書 225・226ページ
まとめ

本記事では、建設業界の方向けに炭素税が建設業に与える影響を解説しました。炭素税は地球温暖化対策を目的とした環境税制度で、化石燃料の使用に伴うCO2排出量に課税することで、温室効果ガスの削減を促進する仕組みです。2028年には炭素税の一種である炭素賦課金が施行される予定です。
建設業では事業活動全般においてCO2の排出が避けられないため、炭素税の影響は特に深刻です。直接的な影響として建設機械の運用コスト増加が挙げられます。炭素税導入により建設業界のコスト構造が大きく変化する中、プロジェクト全体を通じたコスト管理が企業の競争力を左右するより重要な要素となり得ます。炭素税導入に伴う建設業界の技術革新と新たなビジネスチャンスや、戦略的対応も解説しているため、炭素税導入の課題に取り組んでいる方は参照してみてください。

この記事の監修
リバスタ編集部
「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。











