

二酸化炭素を回収し利用CCS∕CCUSとは?課題点や導入状況を解説!

地球温暖化対策として世界中で注目を集めるCCSやCCUS技術は、二酸化炭素を回収して地中に貯留したり有効活用したりする脱炭素技術です。
2050年カーボンニュートラル実現に向けて、火力発電や製造業からの二酸化炭素削減が急務となる中、CCUS技術への期待が高まっています。
本記事では、CCSやCCUSの基本概念から技術的メリット、国内外の導入状況までを詳しく解説します。また、建設業界向けに実用化に向けた課題も解説していますので、建設関連企業で脱炭素に取り組まれている方は参照してみてください。
「CCS」「CCUS」とは?
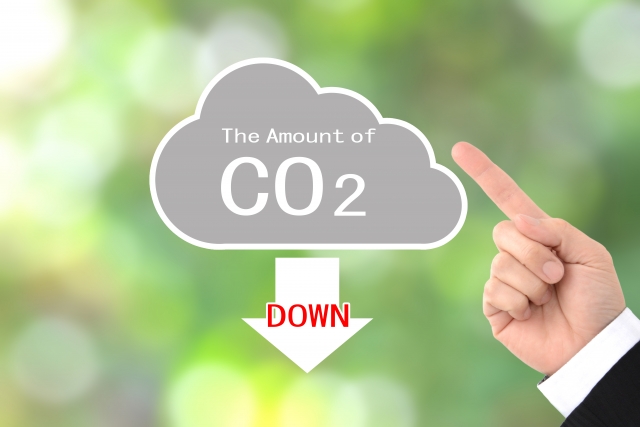
地球温暖化対策として注目を集める「CCS」と「CCUS」は、二酸化炭素の削減に重要な役割を果たす技術です。CCSとは二酸化炭素を回収し地中に貯留する技術であり、一方CCUSとは二酸化炭素を利用する技術として発展しています。
CCSとCCUSの基本概念と技術的な違いについて解説します。
CCSとはCO2を回収し地中に貯留する技術
CCS技術は、産業施設から排出される大量の二酸化炭素を大気中に放出させることなく、地下深くに安全に封じ込める技術です。火力発電所や製鉄所、製油所といった工場では日々膨大な量の二酸化炭素が発生していますが、CCSは排出源から二酸化炭素を直接回収し、地下約800メートル以上の深い地層へと送り込みます。
貯留には地質学的な条件が重要で、二酸化炭素を蓄える砂岩などの多孔質な帯水層と、その上部にある泥岩などの不透水層が組み合わさった構造が必要です。二層構造により、回収した二酸化炭素を長期間にわたって安全に地中に封じ込めることが可能になり、大気中への温室効果ガス排出を大幅に削減できる技術として期待されています。
CCUSとは二酸化炭素を利用する技術
CCUS技術は、回収した二酸化炭素を貯留するだけでなく、有効活用することで経済的価値を生み出すアプローチです。CCUS技術では回収された二酸化炭素を資源として捉え、さまざまな用途に再利用することが特徴です。
特に米国では実用化が進んでおり、回収した二酸化炭素を枯渇した油田に注入する手法が注目されています。この方法では、注入された二酸化炭素が地中に残存する原油を押し出す効果を発揮し、石油の追加採掘を可能にします。
同時に、押し出しの役割を終えた二酸化炭素はそのまま地下に貯留されるため、温室効果ガスの削減効果も得られることが特徴です。
CCS・CCU・CCUSの違い
CCS・CCU・CCUSの技術は、それぞれ異なるアプローチで二酸化炭素削減に貢献します。
それぞれの違いは次の通りです。
| CCS | 二酸化炭素を大気中に排出せずに回収し、貯留 |
| CCU | 二酸化炭素を貯留するのではなく、有用な資源として活用 |
| CCUS | 二酸化炭素を回収・貯留し、さらに資源として活用 |
CCSは回収した二酸化炭素を地中に貯留することに特化した技術である一方、CCUは回収した二酸化炭素を有価値な資源として活用することに焦点を当てています。
CCUSは、CCSとCCUの技術を統合したものとして位置づけられています。
CCS/CCUSが注目される理由
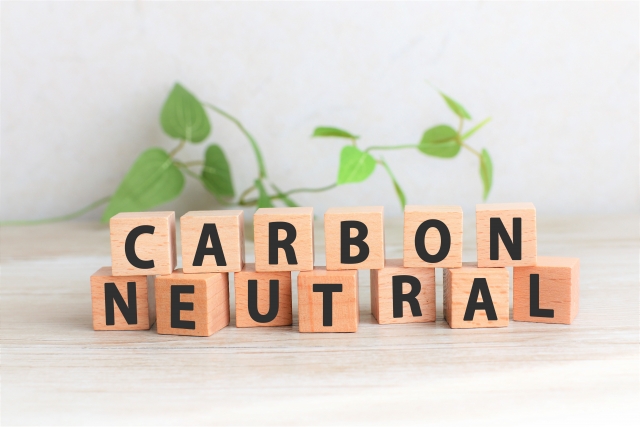
近年、CCSとCCUS技術への関心が世界的に高まっている背景には、深刻化する気候変動問題と国際的な脱炭素への取り組み強化があります。
特に火力発電による二酸化炭素の排出量増加が環境負荷の大きな要因となっており、従来の発電システムからの転換が必要です。CCSとCCUSが注目される理由について解説します。
火力発電による二酸化炭素の排出量増加
火力発電による大量の二酸化炭素排出は、日本の脱炭素における課題の一つです。石油や石炭を燃料とする火力発電は、電力供給の過程で膨大な量の二酸化炭素を大気中に放出し続けており、環境負荷は深刻な問題です。
特に日本では火力発電への依存度が86.1%と極めて高い水準にあり、現在の電力供給体制を維持したままでは2050年カーボンニュートラルの実現は困難な状況にあります。
政府は火力発電の段階的削減と低炭素化を国家戦略として明確に位置づけており、その実現手段としてCCUS技術への期待が高まっているのが現状です。
CCUS技術の導入により、火力発電からの二酸化炭素排出を大幅に削減しながら、安定した電力供給を維持できる可能性があるため、エネルギー転換期における重要な技術として注目を集めています。
2050年カーボンニュートラル宣言による意識の変化
2050年カーボンニュートラル宣言は、CCSやCCUS技術への社会的認識を根本的に変える転機となりました。実際には、技術の基盤となる要素は以前から存在していましたが、実用化に向けた本格的な取り組みは限定的でした。
石油をはじめとする化石燃料が極めて安価に入手できた時代においては、わざわざエネルギーを投入して二酸化炭素を回収し、再利用することは採算面で合理的ではありません。
しかし、政府によるカーボンニュートラル宣言により、環境価値が経済価値として評価される社会への転換が始まり、CCS技術の位置づけが劇的に変化しています。
CCS/CCUSのメリット

CCSとCCUSのメリットとして、次の内容が挙げられます。
- 二酸化炭素の削減が可能
- エネルギーの安定供給
- 産業競争力の向上
それぞれのメリットを解説します。
二酸化炭素の削減が可能
CCSやCCUS技術のメリットは、あらゆる産業分野において二酸化炭素の削減を実現できることです。火力発電所だけでなく、製鉄業やセメント製造業、ごみ焼却施設など二酸化炭素を大量に発生させる幅広い産業分野への適用が可能で、従来では困難とされていた大規模な削減を技術的に実現できます。
具体的な効果を示す例として、約27万世帯への電力供給が可能な出力80万キロワットの石炭火力発電所にCCS技術を導入した場合、年間約340万トンの膨大な量の二酸化炭素を大気中への放出前に回収できることが示されています。
一つの発電所だけでも相当な環境負荷軽減効果があることを示しており、複数の施設や多様な産業分野に展開することで、国全体の排出量削減に大きく貢献できる技術となることがメリットです。
出典:環境省/CCUSを活用したカーボンニュートラル社会の実現に向けた取り組み
エネルギーの安定供給
CCSやCCUS技術は、再生可能エネルギーの課題を解決し、エネルギーの安定供給を実現する重要な役割を果たします。
太陽光や風力などの再生可能エネルギーで生み出される余剰電力の保管手段として水素蓄電技術が注目されていますが、水素の利用には専用インフラの大規模な整備が必要となる課題があります。
一方、CCS技術で回収した二酸化炭素と水素を化学反応させることにより、メタンの製造が可能です。メタンは既存の都市ガス供給インフラをそのまま活用できるため、新たな専用設備への巨額投資を避けながら、効率的なエネルギー貯蔵と供給が実現できます。
そのため、再生可能エネルギーの変動性という根本的な課題を解決しながら、従来のエネルギーインフラを最大限活用した安定的なエネルギー供給システムの構築が可能となり、脱炭素社会への移行をより現実的かつ経済的に進められます。
産業競争力の向上
CCSとCCUS技術は、日本の産業競争力向上に可能性をもたらす技術分野です。日本のエネルギー自給率は約7%と極めて低い水準にあり、燃料の大部分を海外からの輸入に依存している現状が経済安全保障上の課題です。
CCUSにおけるカーボンリサイクル技術の実用化により、国内で発生する二酸化炭素を有効な資源として活用することで、日本の輸入依存体質の改善が期待されます。
具体的には、石油増進回収法による既存油田からの追加採掘技術や、回収した二酸化炭素を原料とした化学品、燃料、コンクリートなどの鉱物製造技術の開発が進んでおり、技術革新により新たな産業分野の創出が可能です。
CCS/CCUS活用の問題点

CCSやCCUS技術は温暖化対策の切り札として期待される一方で、実用化に向けては多くの課題が残されているのが現状です。回収した二酸化炭素を長期間安全に保管するための貯留場所の担保や、新しい技術に対応した法整備の課題も解決すべき重要な問題として浮上しています。
CCSやCCUS活用の問題点について解説します。
実用化に向けた技術的課題
CCSやCCUS技術の実用化には、まだ解決すべき多くの技術的課題が存在しています。二酸化炭素の分離・回収技術は比較的新しい分野であり、現在の技術水準では回収率やエネルギー効率の面で改善の余地が大きく、産業レベルでの大規模導入に必要な性能基準を満たすためには継続的な技術開発が不可欠です。
回収した二酸化炭素を貯留地点まで運搬する際に船舶輸送が重要な役割を担いますが、世界的に見ても大規模な二酸化炭素の海上輸送手段は限られており、安全で効率的な輸送システムの確立が急務です。
輸送過程での二酸化炭素の液化保持技術、船舶の設計基準、荷役システムなど、輸送に関わる一連の技術もさらなる向上が求められています。
二酸化炭素の分離・回収にかかるコスト
CCUS技術における課題の一つが、二酸化炭素の分離・回収にかかる高額なコストです。現在の既存技術を用いて二酸化炭素を分離・回収する場合、経済的負担は大きく、企業にとって導入を妨げる要因となりかねません。
一方で、コストの課題に対する技術開発も着実に進展しており、経済産業省が支援する固体吸収材を活用した新しい分離・回収技術では、従来手法の半分以下のコストで回収が可能になると期待されています。
革新的なコスト削減技術の開発により、CCUS技術の経済性が大幅に改善され、産業界での本格的な導入が現実的な選択肢となる可能性が高まっています。
出典:資源エネルギー庁/知っておきたいエネルギーの基礎用語 ~CO2を集めて埋めて役立てる「CCUS」
二酸化炭素の貯留場所と法整備の課題
CCSとCCUS技術の実用化には、二酸化炭素貯留に関する地質学的条件と法制度の両面で課題が存在しています。
二酸化炭素の安全な貯留条件を満たす適正地の選定は技術的に困難な作業となっているのが現状です。さらに、選定された貯留候補地では地下や海底下における土地所有権や鉱業権といった既存の権利関係が複雑に絡み合っており、権利との競合を回避するための新たな法整備が欠かせません。
また、CCUS事業を実施する事業者の法的責任の範囲や、長期間にわたる貯留層の適正な管理体制も明確な法的枠組みが存在しないため、包括的な法整備を進める必要があります。
CCS/CCUSの導入状況

CCSとCCUSの導入状況として、日本国内と世界それぞれの状況を紹介します。現在の日本がどのような状況に置かれているのか参照してみてください。
日本国内の導入状況
日本国内におけるCCSやCCUS技術の導入は、実証実験段階から実用化に向けた具体的な取り組みへと着実に進展しています。日本初のCCS実証実験として注目された北海道苫小牧でのプロジェクトは大きな成果を収め、2019年11月には当初設定していた貯留目標である累計30万トンの二酸化炭素注入を達成しました。
実証実験により、日本の地質条件におけるCCS技術の有効性が実証され、今後の本格的な展開に向けた重要な基盤が築かれています。一方、CCUS技術の実用化においては、佐賀県佐賀市で画期的な取り組みが実現しており、日本初となるごみ焼却場の廃棄物発電施設への二酸化炭素分離・回収設備の設置が行われています。
出典:苫小牧市企業立地ガイド/苫小牧におけるCCS大規模実証試験
世界の導入状況
世界各国では2018年頃を境にCCS技術開発への取り組みが加速し、国家レベルでの本格的な支援体制が構築されています。米国では経済的インセンティブを活用したアプローチを採用し、CCS事業を税額控除の対象に加えた上で、2022年にはさらなる控除拡大を実施することで民間投資を促進しています。
欧州連合においても大規模な資金支援を決定し、再生可能エネルギーやCCSを含む低炭素化技術に対して10年間で100億ユーロという巨額の支援基金を設立しました。
また、CCS開発の波は新興国にも広がっており、2021年のCOP26を契機としてインドネシアやマレーシアといった東南アジア諸国も脱炭素目標を公表し、国際的なCCS技術開発競争が活発化している状況です。
まとめ

本記事では、CCSやCCUS技術の基本概念から実用化に向けた課題、国内外の導入状況について解説しました。CCSは回収した二酸化炭素を地中に貯留する技術であり、CCUSはさらに利用技術を組み合わせた技術です。
火力発電への依存度が高い日本において、2050年カーボンニュートラル実現のための重要な技術として注目されています。
建設業界においても、CCUS技術を活用し、業界全体の脱炭素に貢献する必要性があります。一方で、技術的課題やコスト問題、法整備の遅れなど解決すべき課題も多く、今後の技術開発と制度整備が普及のポイントです。
建設業界では、入札段階や工事成績評点で施工時や竣工後の建築物においてCO2排出量の削減が評価され、加点につながる動きが生じています。また、建設会社からCO2排出量を開示し削減方針を示さないと、発注者であるデベロッパーから施工者として選ばれにくくなる状況も起きており、建設会社にとってCO2排出量の管理・削減は喫緊の課題です。
リバスタでは建設業界のCO2対策の支援を行っております。新しいクラウドサービス「TansoMiru」(タンソミル)は、建設業に特化したCO2排出量の算出・現場単位の可視化が可能です。 ぜひこの機会にサービス内容をご確認ください。

この記事の監修

リバスタ編集部
「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、
建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。
「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、
建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。
本ウェブサイトを利用される方は、必ず下記に規定する免責事項をご確認ください。
本サイトご利用の場合には、本免責事項に同意されたものとみなさせていただきます。当社は、当サイトに情報を掲載するにあたり、その内容につき細心の注意を払っておりますが、情報の内容が正確であるかどうか、最新のものであるかどうか、安全なものであるか等について保証をするものではなく、何らの責任を負うものではありません。
また、当サイト並びに当サイトからのリンク等で移動したサイトのご利用により、万一、ご利用者様に何らかの不都合や損害が発生したとしても、当社は何らの責任を負うものではありません。


