

風力発電が注目される理由や導入状況について~再生可能エネルギーの可能性とは~
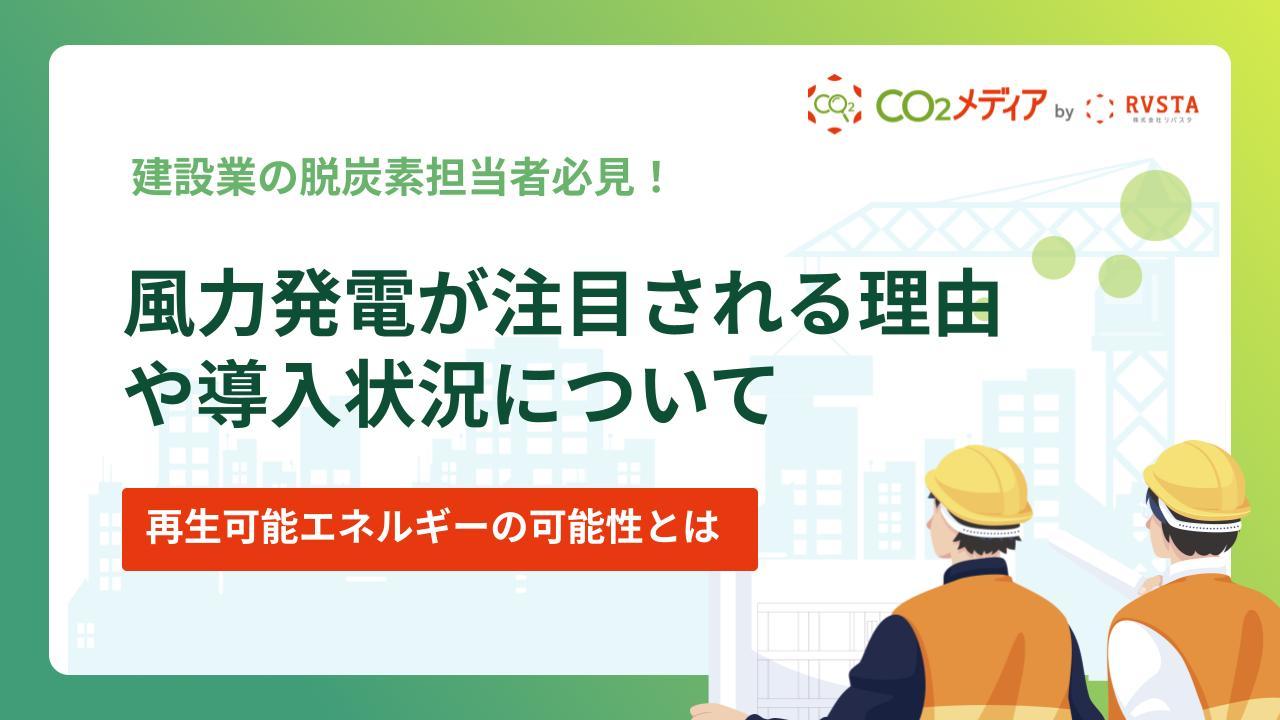
近年、燃料を使用せずに発電でき、さらに長期的なエネルギー安全保障にもつながる風力発電が注目されています。2030年までに、風力発電施設導入を加速する取り組みも公表されました。特に建設業界においては、風力発電施設の設計・施工・インフラ整備といった分野でのニーズが急増しており、新たなビジネスチャンスとしても注目されています。
本記事では、建設業界の方向けに風力発電が注目される理由や導入状況を解説しています。また、洋上風力発電導入の意義や将来性も解説しているため、風力発電に携わっている方は参考にしてみてください。
風力発電の概要

風力発電の概要として次の内容を解説します。
- 風力発電が注目される理由
- 風力発電の仕組み
- 陸上風力発電と洋上風力発電の違い
それぞれの内容を詳しくみてみましょう。
風力発電が注目される理由
風力発電が注目を集める理由として、燃料を使用せずに発電できる点があります。石炭や石油などの化石燃料の購入が不要なため、燃料コストの削減と価格変動リスクの回避につながります。
また、風は自然資源であり、枯渇の心配がありません。風力発電は持続可能な発電が実現するため、長期的なエネルギー安全保障にも貢献します。さらに、風力発電は稼働時にCO2などの温室効果ガスを排出しないため、地球環境への負荷が小さいことも特徴です。気候変動対策が急務となっている現代で、クリーンな特性には価値があります。
風力発電は他の再生可能エネルギーと比較して、効率よく電力を生産できる点で優れています。適切な立地条件下では高い発電効率を実現し、エネルギー変換の面でも効果的な選択肢です。
風力発電の仕組み
風力発電は風のエネルギーを電気に変換する発電方法で、風の力で風車を回転させ、風車の運動を発電機に伝えて発電します。現代の風力発電設備には高度な技術が組み込まれており、風のエネルギーを効率よく電気エネルギーへ変換しています。
例えば、風の強さや方向を計測するセンサーからのデータに基づき、コンピュータ制御システムが風車の羽根の角度や風車全体の向きを自動的に調整可能です。また、自動調整により、様々な状況でも効率的な発電を実現しています。
風車の設計には、一般的な三枚ブレードのプロペラ型風車だけでなく、垂直軸を持つダリウス型風車など、様々な構造の風車があります。それぞれのタイプには特有の利点があり、設置環境に応じて最適なタイプの風車を選択できることも特徴の1つです。
効率的な発電のためには、風が強く安定して吹く場所に風車を設置しなければなりません。そのため、風況の良い場所に複数の風車が集中的に配置されることが多く、風車が集まった場所は「ウインドファーム」または「ウインドパーク」と呼ばれています。
陸上風力発電と洋上風力発電の違い
洋上風力発電は海上や湖面に建設された発電施設です。陸上は、山や建造物の影響で風向や強さが頻繁に変化します。一方、洋上では障害物が少なく、安定した風が吹くため、風力発電に理想的な環境です。洋上ならではの安定性により発電効率が向上し、エネルギー生産量の予測も容易です。
設置環境では、陸上では土地確保や道路幅の制限が課題ですが、洋上では広大なスペースを活用でき、大型発電機の導入が容易にできます。そのため、スケールメリットを活かした発電が可能です。
一方で、風力発電機が波や風の影響で倒壊しないよう、海底に強固な基礎工事が必要なため、基礎工事は高額なコストがかかります。また、発電した電力を陸上に送るための海底ケーブルの敷設費用も距離に比例して増大する点に注意しなければなりません。
さらに、海水や波による浸食作用で設備の劣化が陸上より速く進行するため、維持管理コストも高くなると見積もられています。加えて、洋上での点検・修理作業は天候に左右されやすく、技術的難易度も高くなることが見込まれます。
風力発電のメリットとデメリット
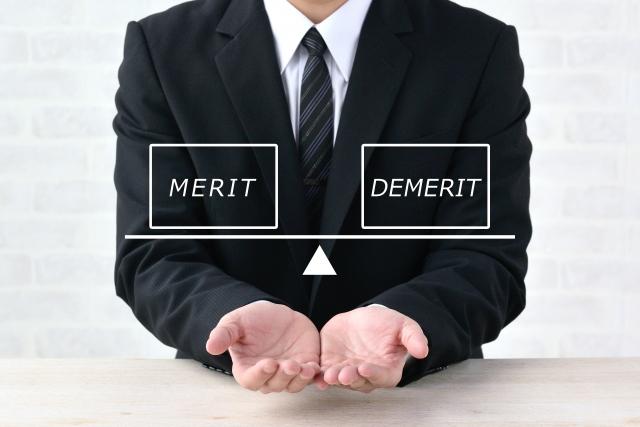
風力発電には、環境負荷が少ないことや昼夜問わず発電できるメリットがある一方で、季節や天候に左右されるデメリットもあります。以下に風力発電のメリットとデメリットをそれぞれ詳しく解説します。
風力発電のメリット
風力発電の重要なメリットは環境面への貢献です。風の力のみで発電するため環境負荷が低く、燃料を燃やす必要がないことから、発電時にはCO2はもちろん、排気ガスや燃えカスなども発生しません。
また、一定の強さの風が担保できる条件下では、太陽光発電と異なり昼夜を問わず連続して発電が可能です。時間帯によらず、電力の安定供給に貢献できます。風力発電設備は陸上だけでなく洋上にも設置できるため、山の頂上付近や洋上など発電が難しい場所でも効率的にエネルギーを生産できます。
経済面では、風力発電はエネルギー変換効率の高さから発電コストが比較的安価な特徴があります。技術発展による大型化・効率化で、経済的にも競争力のあるエネルギー源となってきています。
国内で得られる自然の力を利用する風力発電は、自国資源のみで完結する発電方法であり、エネルギー自給率の向上に貢献すると共に、海外の燃料に依存しない持続可能なエネルギー供給体制の構築を可能にします。
風力発電のデメリット
風力発電のデメリットとして、電力供給の安定性に関する問題があります。自然の風を利用する発電方法であるため、風向きや風速の変動に大きく左右されることがデメリットです。
風が弱まれば発電量は急激に低下し、逆に強すぎる場合は安全のために停止することもあります。そのため、電力を毎日一定量供給が可能かどうか、という安定性の面が他の発電方式に比べて弱点となりかねません。
また、風力発電は季節や気候条件に大きく影響されます。特に台風などの暴風時には、風車のブレードが損傷する危険性があるため、安全対策として稼働を停止させなければなりません。自然条件による運転制限は、年間の発電量や稼働率に影響を与えます。
さらに、風力発電の効率は立地条件に依存することにも注意が必要です。年間を通じて風の強い場所でないと発電効率が著しく悪化するため、建設場所の候補地も自ずと限られてきます。風力発電に適した場所は限られており、そのような場所はすでに開発が進んでいることも少なくありません。このように、設置場所を見つけることが難しいこともデメリットと言えます。
日本における風力発電の現状

日本における風力発電の現状として、陸上風力発電と洋上風力発電それぞれの導入状況を解説します。
陸上風力発電の導入状況
一般社団法人日本風力発電協会の報告によれば、2024年12月時点での日本国内の風力発電の累積導入量は5,840.4MWに達しており、全国で2,720基の風力発電設備が稼働しています。
風力発電の導入が進められていることは日本のエネルギー転換への取り組みを表す重要な指標となっていますが、政府はさらなる導入拡大を目指しています。脱炭素の実現に向けた国家戦略の一環として、風力発電は重要な位置づけです。
政府が掲げる具体的な目標として、2030年度の導入見込量が設定されています。陸上風力発電は17.9GWの目標値が示されています。これは、現在の導入量と比較すると、陸上風力で約3倍の規模です。
この発電目標達成に向けて、送電網の整備や規制緩和、技術開発支援など、様々な施策が講じられていくことが見込まれます。
洋上風力発電の導入状況
洋上風力発電は世界全体で急速に導入が拡大しています。特に欧州を中心に大規模な開発が進められており、再生可能エネルギーの今後を担う重要な柱です。
国際エネルギー機関(IEA)の試算によれば、全世界の洋上風力発電の導入量は2040年には現在の約24倍にまで増加する見込みです。この急成長は、技術の進歩によるコスト低減と、各国の脱炭素政策の強化を背景としています。
日本でも、洋上風力発電の導入を加速させる取り組みが進められています。政府は具体的な目標として、2030年までに10GW、2040年までには30GW〜45GWの導入が掲げられました。目標が達成されれば、一般家庭約600万世帯分の電力をまかなえます。
日本は四方を海に囲まれた島国であり、洋上風力発電の潜在的なポテンシャルは高い国です。特に日本海側や太平洋側の一部海域では、安定した強い風が吹くエリアが広がっており、効率的な発電が期待できます。
洋上風力発電導入の意義

洋上風力発電導入の意義として次の目的が掲げられています。
- 導入拡大の可能性
- コスト競争力のある電源
- 経済波及効果
それぞれの内容を詳しく解説します。
導入拡大の可能性
洋上風力発電は欧州を中心に世界各地で導入が拡大しています。陸上よりも安定して発電できる特徴により、広大な設置スペースを活かした大規模な洋上ウインドファームが次々と建設され、再生可能エネルギーの主力電源としての地位を確立しつつあります。
四方を海に囲まれた島国である日本は、風力発電が盛んな欧州の北海周辺とは地形や状況が異なるものの、欧州の北海周辺と同様に洋上風力発電に適した地理的条件を備えていることが特徴です。日本海側や太平洋側の一部海域では年間を通じて比較的安定した風が吹いており、今後の導入拡大が期待されています。
一方で、防衛レーダーとの干渉問題は、国防の観点から設置場所に制限をもたらす可能性があります。また、日本の沿岸域は伝統的に漁業が盛んであり、漁業関係者との合意形成が不可欠です。
これらの課題を克服するためには、技術的解決策の開発とともに、地域社会との対話や共存モデルの構築が重要です。
コスト競争力のある電源
洋上風力発電は、コスト競争力を高めているエネルギー源です。先行して導入が進んでいる欧州では、めざましいコスト低減が実現しています。遠浅の海域が広がる北海を中心に大規模な導入が進み、発電コストの低減が加速しているのが現状です。
発電事業者による入札では、落札額が10円/kWhを下回る事例が出現するまでになりました。さらに注目すべきは、補助金なしで市場価格のみで事業が成立する案件も登場していることです。
一方で、最近の世界的なインフレーションの影響も無視できません。特に米国や英国では、資材価格の高騰や金利上昇を背景に、一度入札に参加した事業者が撤退するケースも発生しています
日本でも、欧州の成功事例を参考にしながら、地域特性に適した形での導入拡大とコスト低減の両立が求められています。初期投資は大きいものの、燃料費がかからず長期的な発電コストの予測可能性が高い洋上風力発電は、エネルギー安全保障の観点からも重要な電源として欠かせません。
経済波及効果
洋上風力発電は環境面での利点だけでなく、経済的な側面でも意義を持っています。洋上風力発電設備は多くの部品から構成されており、また事業規模も大きいことから、関連産業への波及効果が大きいことが特徴です。そのため、製造業やサービス業など多様な分野での需要創出が期待され、地域経済の活性化に貢献できます。
欧州の港湾都市では、風力発電設備の建設・運転・保守などの地域との結びつきが強い産業が多く育成されています。デンマークのエスビアウ市は代表的な成功例であり、洋上風力関連産業の集積によって企業誘致にも成功し、約8,000人もの雇用を創出しました。
日本でも同様の経済波及効果が期待される一方で、大型風車メーカーが国内に存在しない課題もあります。現状では主要な風車本体は海外からの輸入に依存せざるを得ず、最も付加価値の高い部分の経済効果が国外に流出してしまう懸念があります。
洋上風力発電の将来性

洋上風力発電の将来性として、次の2つの観点が必要です。
- 海域を利用する発電方法
- 洋上風力発電の推進
以下にそれぞれのポイントを解説します。
海域を利用する発電方法
周囲を海に囲まれた日本で、洋上風力発電は特に期待される発電方法です。日本は広大な排他的経済水域を有しており、海洋資源を再生可能エネルギー生産に活用することは重要な意味を持ちます。
陸上風力発電は開発が進み適地が減少してきていることから、新たな設置場所として海域を利用した洋上風力発電への注目が高まっています。しかし、洋上風力発電は海域を長期間にわたって占用することになるため、漁業や海運など既存の利用との調和が不可欠です。また、厳しい海洋環境下での設備の維持管理も重要な課題です。
課題に対応するため、占用者の選定基準や手続きの明確化をしなければなりません。この課題解決へ向けて日本政府は「再エネ海域利用法」を制定し、透明性の高い公募プロセスを通じた事業者選定の仕組みを構築しています。
参照:経済産業省/「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました
洋上風力発電の推進:EEZに拡大
日本政府は洋上風力発電の設置場所を現行の領海内から排他的経済水域(EEZ)にまで拡大する再生可能エネルギー海域利用法の改正案を閣議決定しました。海に囲まれた日本の強みを活かし、再生可能エネルギーの適地を広げることで、2050年までの温室効果ガス排出量実質ゼロを目指します。
技術面では、EEZの深い海域では風車を海面に浮かべる浮体式が主流になる見通しです。現在主流の海底に固定する着床式と異なり、浮体式は深い海域にも設置できるため、利用可能なエリアが大幅に拡大します。
一方で、EEZでは領海に比べて、事業者が利用許可を得るまでの過程が2段階に増えます。海洋環境や既存の海域利用との調和を図りながら、計画的な開発を進める体制を整備しなければなりません。
まとめ

風力発電が注目を集める理由として、燃料を使用せずに発電できる点があります。石炭や石油などの化石燃料の購入が不要なため、燃料コストの削減と価格変動リスクの回避につながります。
また、洋上は障害物が少なく、安定した風が吹くため、風力発電に理想的な環境です。このため、洋上ならではの安定性により発電効率が向上し、エネルギー生産量の予測も容易です。
日本でも、洋上風力発電の導入を加速させる取り組みが進められています。政府は具体的な目標として、2030年までに10GW、2040年までには30GW〜45GWの導入が掲げられました。
本記事では、建設業界の方向けに風力発電、特に洋上風力発電導入の現状や意義、さらに洋上風力発電の将来性も解説しているため、風力発電に携わる方は参考にしてみてください。
建設業界では、入札段階や工事成績評点で施工時や竣工後の建築物においてCO2排出量の削減が評価され、加点につながる動きが生じています。また、建設会社からCO2排出量を開示し削減方針を示さないと、発注者であるデベロッパーから施工者として選ばれにくくなる状況も起きており、建設会社にとってCO2排出量の管理・削減は喫緊の課題です。
リバスタでは建設業界のCO2対策の支援を行っております。新しいクラウドサービス「TansoMiru」(タンソミル)は、建設業に特化したCO2排出量の算出・現場単位の可視化が可能です。 ぜひこの機会にサービス内容をご確認ください。

この記事の監修

リバスタ編集部
「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、
建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。
「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、
建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。
本ウェブサイトを利用される方は、必ず下記に規定する免責事項をご確認ください。
本サイトご利用の場合には、本免責事項に同意されたものとみなさせていただきます。当社は、当サイトに情報を掲載するにあたり、その内容につき細心の注意を払っておりますが、情報の内容が正確であるかどうか、最新のものであるかどうか、安全なものであるか等について保証をするものではなく、何らの責任を負うものではありません。
また、当サイト並びに当サイトからのリンク等で移動したサイトのご利用により、万一、ご利用者様に何らかの不都合や損害が発生したとしても、当社は何らの責任を負うものではありません。


