

中小企業がGXに取り組むメリットは?活用できる補助金も紹介
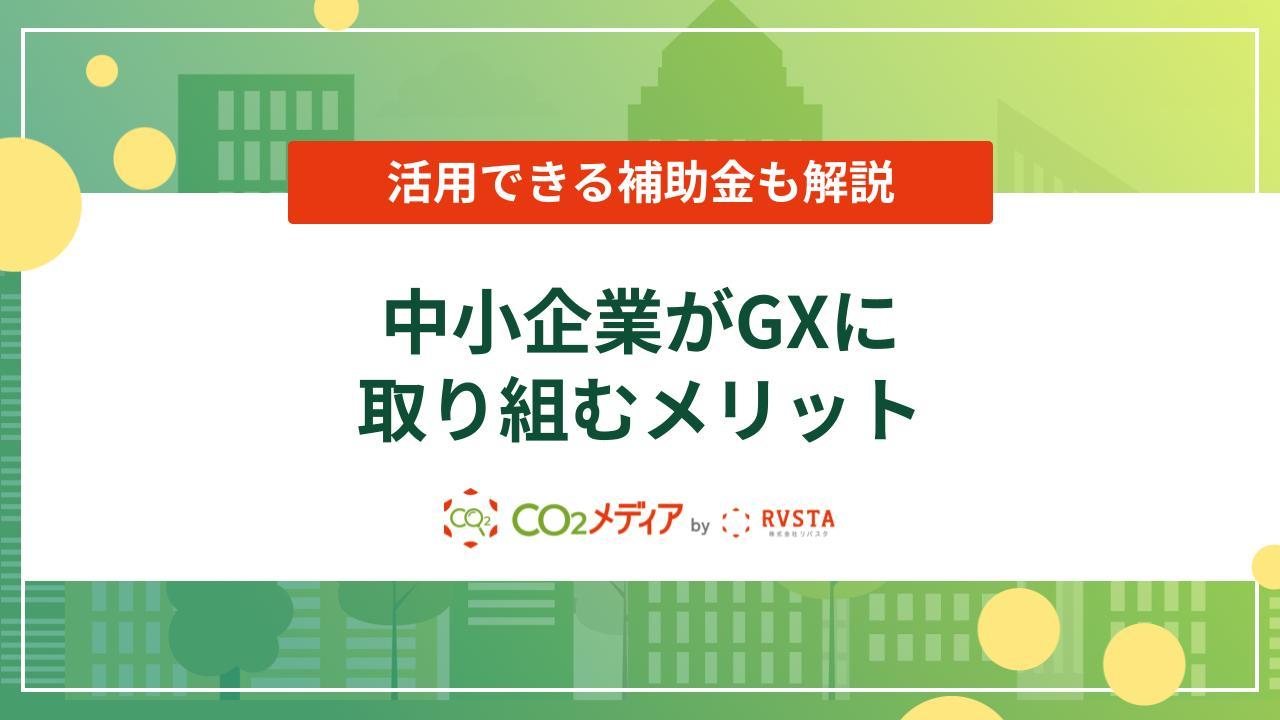
GXへの取り組みは、建設業界の中小企業にとって取引先の確保や事業展開などさまざまな面から今後も求められていくことが予想されます。一方で、情報が少ないことや設備投資へのコストが課題としてあるのが現状です。
本記事では、中小企業がGXに取り組むメリットを解説しています。また、GXへ取り組む際の課題や、活用できる補助金も紹介しているため、GX導入を検討している方は参考にしてみてください。
GXについて

中小企業では、脱炭素化と並行して、GX(グリーントランスフォーメーション)への取り組みが重要な一環として求められています。
GXについて次のポイントをそれぞれ解説します。
- GXとは
- 脱炭素に向けた取り組み状況
- GX推進法と政府の取り組み
それぞれの内容を詳しくみていきましょう。
GXとは
GXは、化石燃料依存からの脱却とクリーンエネルギーを積極的に利用する社会への転換を目指すものです。このGXには、2050年までの脱炭素社会実現に向け、産業構造や社会システムの全面的な変革が含まれます。
建設業界では、国土交通省が公共工事で低炭素材料の使用を積極的に推進しており、従来の資材からCO2排出量の少ない環境配慮型の材料への転換を進めています。また、例えばICT施工の導入により、建設現場での作業の効率化と同時に、燃料消費量の削減による温室効果ガスの排出削減を実現していかなければなりません。
さらに、建設機械も、従来のディーゼルエンジンから、電動化や水素燃料、バイオマスなどのグリーンエネルギーを活用した革新的な機械への移行が進められています。GXは建設業界全体での脱炭素に向けた包括的な変革を促進する取り組みです。
脱炭素に向けた取り組み状況
脱炭素に取り組む企業は着実に増加しており、具体的な取り組みも徐々に進展しています。一方で、多くの企業では気候変動対応やCO2削減の重要性は認識しているものの、実際の行動に移せていない状況が続いているのが現状です。
中小企業は、脱炭素の必要性を理解しながらも、実際の取り組み開始まで多くの障壁に直面しており、具体的なアクションに移せないケースが多いです。しかし、取引先からの排出量計測や脱炭素協力の要求が2020年から2022年にかけて2倍に増加しており、中小企業も取り組みを行う必要性が高まっています。
グローバルなサプライチェーン全体で脱炭素への取り組みが加速する中、日本企業も国際的な要請に応えるべく、具体的なアクションを起こすことが急務です。企業の規模に関わらず、脱炭素は避けて通れない経営課題として認識され始めています。
GX推進法と政府の取り組み
日本政府は、2050年までの脱炭素社会の実現に向けて、地球温暖化対策と経済成長の両立を目指すGXの推進に取り組んでいます。GXを進める一環として、2022年7月にGX推進法を成立させ、政府、地方自治体、民間企業が一体となって脱炭素社会への転換を進める法的基盤を整備しました。
GX推進の主な施策は次の通りです。
| 項目 | 内容 |
| GX戦略の策定・実施 | 政府が、GXの推進に関する基本的な方針を定め、GX戦略を策定し実施をする |
| GX推進計画の策定・実施 | 地方公共団体が、GXの推進に関する計画を策定し実施する |
| GX推進のための支援 | 政府が、GXの推進に関する研究開発や普及啓発などを支援する |
GX推進法は、GX推進の基本方針を定め、企業や自治体に炭素排出削減と再生可能エネルギーの導入を奨励する施策を含んでいます。特に、企業の取り組みを後押しするため、GX関連の技術開発や事業展開に対する支援策や補助金制度が設けられました。
日本政府は法整備と具体的な支援措置を通じて、産業界全体のGXを促進し、環境保全と経済発展の好循環を生み出す社会システムの構築を目指しています。
GX導入することによる中小企業のメリット

GX導入による中小企業のメリットは以下の通りです。
- エネルギーコストの削減
- 取引先の確保
- 新たな事業展開が可能
GX導入によりどのようなメリットを受けられるのか、詳しくみていきましょう。
エネルギーコストの削減
GXは、脱炭素や温室効果ガスの排出削減を目指す取り組みですが、環境への貢献だけでなく、中小企業にとってエネルギーコストの削減の点で経営メリットをもたらします。特に昨今のエネルギー価格高騰を考えると、コスト削減効果は企業経営で欠かせない要素です。
例えば、工場や自社施設の屋根に太陽光パネルを設置して自家発電を行うことで、外部から購入するエネルギー量を減らせます。太陽光パネルの設置により、月々の電気代を大幅に削減できるだけでなく、エネルギー価格の変動による経営リスクも軽減可能です。
さらに、省エネ機器の導入や照明のLED化、空調設備の効率化など、さまざまな取り組みを組み合わせることで、より大きなコスト削減効果を得られます。GXへの取り組みは、環境保護と経営改善の両立を可能にする有効な戦略です。
取引先の確保
GXの推進は、中小企業にとって取引先の確保のメリットをもたらします。環境問題に積極的に取り組む企業としてのイメージを確立することで、企業ブランドの新たな価値創造が可能となり、取引先との関係強化や新規取引先の開拓につながります。
特に近年、大企業はサプライチェーン全体での脱炭素を推進しており、取引先の選定で環境への取り組みを重視する傾向が強まってきました。そのため、GXに積極的に取り組む中小企業は、取引先としての優位性を確保できます。
実際に、多くの大企業が取引先に対してCO2排出量の削減目標の設定や再生可能エネルギーの導入を求めているのが現状です。このような状況下で、早期にGXに取り組むことは、将来的な取引機会の確保や事業の継続性を高める重要な経営戦略です。
GXの推進は、単なる環境対策ではなく、企業の競争力強化につながる投資として捉えられます。
新たな事業展開が可能
GX推進を通じて、中小企業は既存の技術を活用して新たな成長分野に進出可能です。GX推進によって、環境配慮型の製品やサービスへの需要増加に対応し、企業の持続的な成長を実現する機会となることが見込まれます。
ガソリン車関連部品の製造を行っている金属加工企業では、既存の技術基盤を活かしながらEV関連部品の製造にも着手することで、急速に拡大するEV市場の需要に対応可能です。また、最先端設備への戦略的な投資により、高精度加工技術を磨き、全固体蓄電池など次世代デバイスの製造にも対応できる体制を整えられます。
GXへの取り組みは、環境対応の側面だけでなく、新規市場への参入や事業領域の拡大など、企業の新たな成長機会を創出する重要な経営戦略にもなります。
中小企業によるGXへの課題
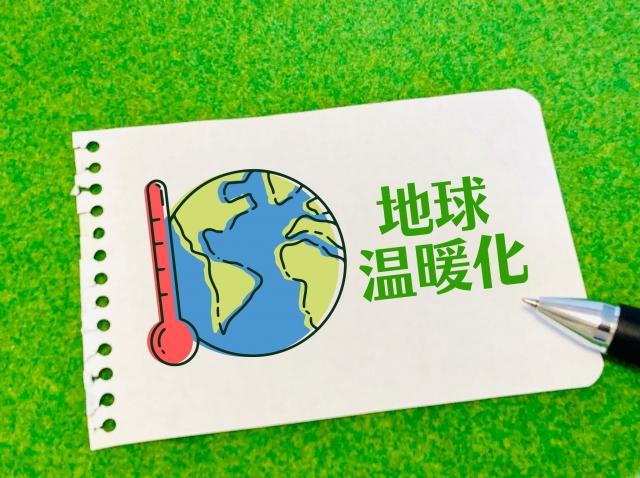
中小企業がGXに取り組む際に直面する主な課題は以下の通りです。
- 情報が少ない
- 設備投資へのコストが大きい
- 技術的な課題
以下にそれぞれのポイントを解説します。
情報が少ない
GXの重要性は徐々に認識されていますが、中小企業にとって大きな課題については情報不足であり、何から始めていいか分からない状況にあります。フォーバルGDXリサーチ研究所の調査によると、多くの企業が「光熱費や燃料費の節約」や「温室効果ガス排出量の測定」などの基本的な取り組みに対して、具体的な実施方法がわからず着手できていない状況にあることが公表されています。
つまり、GXへの取り組みが難しい主な理由は、基本的な知識や実践的なノウハウの不足にあります。
GXへの取り組みを始める際には、まず業界団体や支援機関などを通じた情報収集から着手し、自社に適した取り組み方法を見出していくことが重要です。
設備投資へのコストが大きい
GXを実現するには、生産設備や業務プロセスを大幅に刷新する必要があり、これが中小企業にとって大きな負担となることがあります。GXに向けた投資は多額の資金を必要とするだけでなく、リスクも高い特徴があります。
事業のグリーン化には運営コストが上昇する可能性があり、投資に対する収益が保証されるわけではありません。設備投資へのコストに対する課題に直面する中小企業の負担を軽減するため、政府はさまざまな支援策を講じています。
例の1つがカーボンニュートラル投資促進税制で、近年では優遇措置の期間延長や税制の見直しが実施され、企業のGX投資を後押ししているのが現状です。支援制度を効果的に活用することで、中小企業も段階的にGXへの投資を進められます。
技術的な課題
GXの推進には革新的な技術開発が不可欠ですが、現状ではさまざまな技術的課題に直面しています。特に、再生可能エネルギーの分野では、効率性の向上とコスト削減が大きな課題で、継続的な技術革新が求められています。
例えば、太陽光発電や風力発電は、天候条件によって発電量が大きく変動するため、安定した電力供給が難しいことが課題です。課題に対応するため、蓄電池の開発や、バイオマス発電、地熱発電との組み合わせによるハイブリッド発電システムの導入が進められていますが、まだ完全な解決には至っていません。
また、温室効果ガスの回収・貯留・利用を行うCCS・CCU技術は、実用化に向けた取り組みが進められているものの、コストや安全性の面でさらなる改善が必要です。技術的課題を克服し、実用的なソリューションを開発・普及させるには、相当の時間と投資が必要となることが見込まれます。
中小企業のGXに向けた補助金

中小企業のGXに向けた補助金として、次の4つの補助金を紹介します。
- 中小企業等事業再構築促進事業
- SHIFT事業
- ものづくり補助金
- 日本公庫による環境・エネルギー対策資金
それぞれの詳しい特徴を解説します。
中小企業等事業再構築促進事業
中小企業等事業再構築促進事業は、ポストコロナ時代の事業再構築を支援する補助金制度です。特に、グリーン成長戦略の実行計画で定められた14分野における課題解決に取り組む事業者に対しては、GX進出類型として通常よりも手厚い支援が提供されています。
この制度では、中小企業は最大6,000万円の補助を受けることができ、対象費用の50%が補助されます。補助対象となる経費は幅広く、建物の建設・改修費用、機械装置の導入費、システム構築費に加えて、広告宣伝・販売促進にかかる費用、従業員の研修費用なども補助対象です。
このように、中小企業等事業再構築促進事業は中小企業のGXへの取り組みを資金面から強力にサポートし、環境配慮型のビジネスモデルへの転換を促進する重要な支援策として期待されています。
参照:事業再構築補助金第13回公募の概要|経済産業省 中小企業庁
SHIFT事業
SHIFT事業は、2030年度の温室効果ガス削減目標達成と2050年の脱炭素社会の実現に向けて、工場・事業場における脱炭素のモデルとなる取り組みを支援する制度です。SHIFT事業では、中小企業等の工場・事業場のCO2削減目標・計画の策定を支援しています。
また、Scope3削減に取り組む企業が主導して、サプライヤー等の工場・事業場のCO2排出量削減に向けた設備更新を促進する取り組みなどもサポート対象です。支援内容は多岐にわたり、補助上限額や補助率は取り組む内容や規模によって異なります。
特に、大規模電化・燃料転換事業では、補助額が最大5億円と手厚い支援が用意されており、企業の大規模な設備投資を後押ししています。SHIFT事業は企業の脱炭素への取り組みを支援する重要な制度です。
参照:SHIFT事業|環境省
ものづくり補助金
ものづくり補助金は、中小企業の生産性向上を目的とした設備投資やシステム導入を支援する制度です。ものづくり補助金は業種を問わず、生産性向上につながる設備投資であれば幅広く活用できます。
特に成長分野進出類型では、GXに資する革新的な製品・サービス開発のための設備投資等に対して、通常よりも高い補助上限額と補助率が設定されていることが特徴です。環境に配慮した製品開発や生産プロセスの革新を目指す企業を重点的に支援しています。
取引先からCO2排出量の削減を求められている企業が、生産性向上と脱炭素を同時に実現するための設備投資を行う際にも活用できる、実践的な支援制度です。ものづくり補助金では、中小企業の競争力強化と環境対応の両立を促進しています。
日本公庫による環境・エネルギー対策資金
日本公庫による環境・エネルギー対策資金は、日本政策金融公庫が実施する融資制度の1つで、中小企業のGX推進を資金面からサポートする制度です。
GX推進計画の実施に必要な設備投資や、GX推進に伴う長期運転資金の調達を支援しており、脱炭素に向けた設備導入や省エネルギー化のための施設改修など、幅広い用途に活用できます。
返済期間や利率は次の通りです。
| 名目 | 返済期間 | 据置期間 | 利率 |
| 設備資金 | 20年以内 | 2年以内 | 4億円まで 特別利率 ※条件あり
4億円超 基準利率 |
| 運転資金 | 7年以内 | 2年以内 | 基準利率 |
中小企業が環境負荷の低減と事業の持続的発展を両立させるための、重要な資金調達手段です。
まとめ

本記事では、建設業界の方に向けて中小企業がGXに取り組むメリットを解説しました。GXとは、化石燃料への依存から脱却し、クリーンエネルギーを活用する社会への転換を目指す取り組みです。
GX導入によって、環境への貢献だけでなく経営戦略に関するメリットが得られます。コストの削減や、イメージ向上による取引先の確保、既存事業にはない新たな事業展開などが可能となることが見込まれます。
一方で、GXの実現には、生産設備や業務プロセスの大規模な刷新が必要となり、中小企業にとって大きな設備投資負担となりかねません。
GXに向けた取り組みで活用できる補助金を紹介しているため、GX導入を検討している方は参考にしてみてください。
建設業界では、入札段階や工事成績評点で施工時や竣工後の建築物においてCO2排出量の削減が評価され、加点につながる動きが生じています。また、建設会社からCO2排出量を開示し削減方針を示さないと、発注者であるデベロッパーから施工者として選ばれにくくなる状況も起きており、建設会社にとってCO2排出量の管理・削減は喫緊の課題です。
リバスタでは建設業界のCO2対策の支援を行っております。新しいクラウドサービス「TansoMiru」(タンソミル)は、建設業に特化したCO2排出量の算出・現場単位の可視化が可能です。 ぜひこの機会にサービス内容をご確認ください。

この記事の監修

リバスタ編集部
「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、
建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。
「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、
建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。
本ウェブサイトを利用される方は、必ず下記に規定する免責事項をご確認ください。
本サイトご利用の場合には、本免責事項に同意されたものとみなさせていただきます。当社は、当サイトに情報を掲載するにあたり、その内容につき細心の注意を払っておりますが、情報の内容が正確であるかどうか、最新のものであるかどうか、安全なものであるか等について保証をするものではなく、何らの責任を負うものではありません。
また、当サイト並びに当サイトからのリンク等で移動したサイトのご利用により、万一、ご利用者様に何らかの不都合や損害が発生したとしても、当社は何らの責任を負うものではありません。


